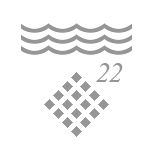ディキンソン 「詩人はランプに火を点すだけ――」 The Poets light but Lamps —
海外の詩の翻訳シリーズ。
エミリー・ディキンソン、第7回「詩人はランプに火を灯すだけ――」 The Poets light but Lamps — (883番 1864年)日本語訳と解説(ディキンソンの目次と年譜はこちら)。
1.日本語訳 2.原詩 3.解説 4.翻訳ノート
5.亀井俊介の解説について
※ [ ]は、わたしの補足です。
※ 『対訳 ディキンソン詩集』亀井俊介編(岩波文庫)、『ディキンスン詩集』新倉俊一訳・編(思潮社)を翻訳と解説の参考にしました。
日本語訳 詩人はランプに火を点すだけ――
詩人はランプに火を点すだけ――
自らは――立ち去る――
ランプの芯[こころの中心]を活気づける――
そこに生命の光があると思えるなら
灯は恒星の明るさを内に秘めて――
各々の時代はレンズの役割を担う
伝い拡がってゆく
光の輪が――
原詩 The Poets light but Lamps —
The Poets light but Lamps —
Themselves — go out —
The Wicks they stimulate —
If vital Light
Inhere as do the Suns — 5
Each Age a Lens
Disseminating their
Circumference —
参考:https://en.wikisource.org/wiki/The_Poets_light...
※ 原詩は版によってカンマやダッシュ、大文字、小文字の使い分けなどに違いがある場合があります。こちらでは『対訳 ディキンソン詩集』で使われているテキストThomas H. Johnson: The Poems of Emily Dickinson, 1955に合わせました。
解説 時代に所属する詩人
ここでのディキンソンは、詩人(作家)― 詩(作品)― 読者(鑑賞者)、芸術の基本となる三つの関係に時代の要素を加えて歌っている。それぞれの行を順番に見てゆこう。
1行目、ランプは読者であり、点される火(着火のための火)は詩だと思う。2行目、詩人は読者に詩を届けると立ち去る(詩人は論じたり、お説教したりしない)。3行目、点された火(詩)はランプの芯=こころの中心(自己)をゆたかに活気づける(鼓舞する)。4行目、詩と読者の協調作用から「生命の光」が生じる(ここに詩の不思議があると思う)。光は、わたしたちの生(この世界に生きて在ること)をその内側から明るく照らしてくれる。
第1連で呈示されたランプの灯~生命の光が、第2連(5行目)で恒星~夜空の星々へと展開される。恒星のイメージは詩の永遠性、詩の世界が持つミクロコスモを暗示しているようにも思われる。6行目でディキンソンは時代をレンズ(光を拡散する機能を持つ)に結びつける。ここに呈示されたのが「時代」であることに注目したい。わたしのお気に入りの作家安部公房はガルシア=マルケスについて「時代」をキーワードに次のように語っている(講演「地球儀に住むガルシア・マルケス」より)。
マルケスの魅力は、まずどこの作家というような所属の括弧からはずれたところにあると思う。あえて所属を言うならむしろ時代でしょう。空間よりも時間、地域よりも時代に属する作家なんだ。(……)マルケスの文学は[地域~ローカルな視点を越えた]世界に辿り着いている。
※ [ ]は、わたしの補足です。
この文章はマルケスをディキンソンに置き換えてもそのまま読めてしまう(と思う)。19世紀後半、アメリカの片田舎でひっそりと暮らしながら、ディキンソンはそのような時代性への眼差しをどのようにして獲得したのだろう? それが詩人というもの? (すごいね、ディキンソン!)
参考:安部公房は、そのようなタイプの作家が目立ってくるのは1930年代くらいからではないだろうか、と語っていて、それはディキンソンの詩がアメリカ文学史に取り上げられはじめた頃に一致する(詳細はディキンソンの年譜を参照)。
7~8行目、「個」の内面を照らす光が時代~レンズによって拡散される(この拡散は同時代性としてとらえたい)。それぞれの時代の内なる光が波紋のように外へ外へと伝い拡がってゆき、あらたな円周=世界が獲得される。最終行に描かれた拡がる光の輪(光の波紋)のイメージはとても美しい。
第1連はディキンソンが先人の詩人たちから受けとったものを、第2連は自身の詩の時代への可能性(確信)を歌ったものかなという気がしている(皆さんはどのように思われますか?)。
翻訳ノート
この作品は訳すのにずいぶんと時間がかかった。各行を日本語の詩として自然に展開してゆきたいのだけれど、これがなかなかむつかしい(むむむ…)。今回は各行のイメージ~展開がより明確になる方向で原詩にいくらか言葉を盛りつつ訳していった。
第1連
1行目、3行目「活気づける」への展開~流れを考えて「火」のイメージを組み込んで、「ランプに火を点す~」としてみた。
2行目 go out 既存の訳はなぜか「消える」の方向で訳してある。情景から考えると暗かった部屋(こころ)に詩人がランプを灯してくれて、詩人は部屋から出てゆくというようなことなので「出てゆく」の方向から「立ち去る」とした(このあたり、詩人のむやみに自己主張しない謙虚なさまが感じられて素敵です、わたしもそのようでありたい…)。
3行目 stimulate 「刺激する、活気づける、鼓舞する」は、ランプの芯を「自己~こころの中心」と理解して「活気づける」と訳した(もう少しぴったりとした言葉があるかもしれない)。わたしの訳の理解(解釈)を明確にするために「ランプの芯[こころの中心]」と意味を補足した。
4行目 vital Light は「生命の光」と訳してみた。vital のニュアンスとしては「生命の維持に必要な~」ということで、光=詩の持つエナジーと人間の〈生〉とがつよく結びつけられた表現になっているようです。
第2連
5行目 the Suns 「複数形だから「恒星」だが、訳文は「太陽」としておいた」(亀井俊介の解説)ということですが、詩の情景は「夜」なので(ランプは夜に灯されるので)、ここに太陽のイメージを組み込むのはいまひとつ気がひける。そのまま恒星(夜空の星々~精神のミクロコスモ)の方向で訳すのがよいのではないだろうか。
6行目、原詩に「(レンズの)役割を担う」と言葉を盛って、行の意味がより明確になる方向で訳した。
7~8行目、言葉数はわずか3語なのだけれど、これをどのように訳すのがよいのか、ずいぶんと時間をかけて検討した。いつも参考にさせてもらっている既存の訳は直訳ふうで次のようになっている。
押しひろげます
円周を――※ 亀井俊介訳
円周を
大きくひろめながら――※ 安藤一郎訳
これだと詩の終え方として弱い気がするし、内容を直感的に把握しずらいように思う(わたしの印象)。この翻訳シリーズは個人的な試みの要素もおおきいので(それを楽しみにやっているので)、もう少し突っ込んで訳してみたい(さてどうしたものか…)。
ひとつ前の行(6行目)でレンズのイメージが呈示される。レンズは光を屈折する機能があるので、拡がってゆく円周は光の円周というふうに考えられる。Circumference 「円周」→「光の円周」から「光の輪」という言葉が直感的に思い浮かんだ。これじゃないのか? (小さなひらめきだった)
時代を構成する個人に内在する光(=詩)が、ひとからひとへと伝わり(リレーされて)拡がってゆく。それを遠くから眺めれば、暗い夜~わたしたちの時代に光の輪が拡がってゆくように見える。最終2行を、このようなイメージでとらえて、
伝い拡がってゆく
光の輪が――
と訳してみた。
この詩の訳は、あれこれ試行錯誤しても納得のゆく仕上がりにならず、ひと月あまり放置していた時期があった。結果として、この放置していた時間がよかったのかもしれない。
参考 亀井俊介の解説について
わたしはこの作品を詩人―詩―読者の関係に時代の要素(視点)を加えて読んだ。亀井俊介はそれとは違う理解(解釈)で、次のように解説されている。
ディキンソンの詩人論、ないし詩論ともいえる作品。詩人から独立して生きる「詩」そのものを、詩人が火をともすランプの芯にたとえる。その芯が「生命の光」をもって燃えるならば、それぞれの時代がレンズとなって、その輝きを周辺にひろげる、という。(……) ディキンソンは自己を強固にすると同時に、それを周辺に投射することを詩人の仕事としていたようだ。
この解説では「ランプの芯」=「詩」ということだけれど、そこに詩人が火をともすとはどういうことだろう? わたしは詩もつくるけれど、出来上がった詩に作者が火をともすということがどういうことなのか、よく分からない。そしてなにより、ここには読者が出てこない(大切な指摘)。読者不在の詩とは? 批判的なことはあまり語りたくないけれど、このような解釈の背景にはアカデミックな立場からの講壇的思考が透けて見えるような気がして残念に思った(解釈には解釈するひとの資質や性向が反映される)(このあたり詳細に語ると長くなりそうなので以下省略)。
詩は(ありがたい神さまのように)人々を、あるいは世間を無条件に照らしたりはしない。詩は読者に読まれることによって、それぞれの内面で独自の光を生じる。お気に入りの詩句を持つひとなら、この感覚はよくわかると思う(どうですか?)。そのようにして獲得された光(詩)は人生をゆたかにしてくれる、つよくしてくれる、この世界をよりよく生きるための道標になってくれる。詩とはそのようなものではないだろうか(参考ということで…)。
- 次回 「お別れはしないでおきましょう」(第8回)
- 前回 「わたしが死へと立ち止まれなかったので――」(第6回)
ご案内
- エミリー・ディキンソン 詩と時代~年譜 (目次)
ディキンソン おもな日本語訳