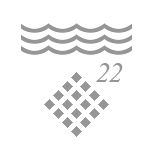ディキンソン 「憑かれるのは――部屋でなくてよい――」 One need not be a Chamber — to be Haunted —
海外の詩の翻訳シリーズ。
エミリー・ディキンソン、第12回「憑かれるれるのは――部屋でなくてよい――」 One need not be a Chamber — to be Haunted — (670番 1862年)日本語訳と解説(ディキンソンの目次と年譜はこちら)。
※ [ ]は、わたしの補足です。
※ 『ディキンスン詩集』新倉俊一訳・編(思潮社)を翻訳の参考にしました。
日本語訳 憑かれるれるのは――部屋でなくてよい――
憑かれるれるのは――部屋でなくてよい――
家でなくてよい――
頭のなかの通路は――それらを越えている
実在の場所より
遙かに安全なのは 真夜中に遭遇する
外の亡霊の方なのだ
内で向かいあう――
冷たいホスト[こころの在り処]より
遙かに安全なのは 修道院を
石[投石]に追われて駆けてゆく方なのだ――
ありのままの自分自身と丸腰で出会うより――
寂しい場所で――
「わたし」の背後に「わたし」が隠れている――
そのことにいちばん驚く――
わたしたちのアパートに隠れている暗殺者は
少しも怖くない
肉体を――リボルバーで武装して――
ドアの掛けがねを締めても――
高位[精神世界]の亡霊は見逃してまう――
あるいはそれ以上の――
原詩 One need not be a Chamber — to be Haunted —
One need not be a Chamber — to be Haunted —
One need not be a House —
The Brain has Corridors — surpassing
Material Place —
Far safer, of a Midnight Meeting 5
External Ghost
Than its interior Confronting —
That Cooler Host.
Far safer, through an Abbey gallop,
The Stones a'chase — 10
Than Unarmed, one's a'self encounter —
In lonesome Place —
Ourself behind ourself, concealed —
Should startle most —
Assassin hid in our Apartment 15
Be Horror's least.
The Body — borrows a Revolver —
He bolts the Door —
O'erlooking a superior spectre —
Or More — 20
参考:https://en.wikisource.org/wiki/One need not be...
※ 原詩は版によってカンマやダッシュ、大文字、小文字の使い分けなどに違いがある場合があります。
解説 自我と自己 「わたし」に隠された「わたし」
自己意識をめぐる興味深い作品。現実世界(外界)より、こころの世界(内界)の方がはるかに危険であり、「わたし」の背後に「わたし」が隠れていることにいちばん驚くという。
一般に西洋(キリスト教文化圏)では「わたし(存在)」と自我(ego)の結びつきがつよい。「自我は人間の意識の中心であり、その主体として存在している。そのような独立した自我を確立するために西洋の文化は多大なエネルギーを費やしてきた」(河合隼雄『ユング心理学入門』培風館より)
意識の中心である自我は「わたし」をまとまりのある体系として基礎づけてゆく。そうすることで個別化(個性化)された「わたし」が獲得されてゆくわけだけれど、それがそのままこころ全体の安定につながるかというと、そうでもない(心理学からの考察)。自我を形成してゆく過程で意識からはこぼれ落ちていった何か、あるいは相容れなくて拒まれた何か、そのような意識下へと役割を割り振られた何かが、ふと spectre 「亡霊(怖ろしい幻影)」となって現れ、自我をおびやかすこともある。
心理学者のカール・グスタフ・ユング(Carl Gustav Jung, 1875-1961)は、わたしたちのこころのモデルをつぎのような球体として描いた。

意識の中心としての自我と全体性の中心としての自己の図(河合隼雄『ユング心理学入門』を参考にして作画しました)。
河合隼雄の著作で、このような自我と自己の関係を示されたとき、ああ、なるほど! と深く感心した。意識の領域ではなく、無意識の領域に「わたし」の全体性の中心=自己(self)を置いたモデルは、わたしたちのこころの在り方におおくの示唆を与えてくれると思う。
詩は5つの連からつくられていて、各パートで現実世界とこころの世界が並べて置かれる。詩の語り手は終始、こころの世界の危うさを説く。現実世界に対して有効な武器であるリボルバー(回転式拳銃)も、こころの世界の死角から立ち現れてくる亡霊を阻止することは出来ないという(最終連)。だとしたら、「わたし」はどのように「わたし(自我)」を守ればいい? 「わたし」から……
第3連(9~10行目)に修道院から追われる情景が描かれる。これはキリスト教の信仰から追放されるイメージが重ねられてるようにも思われる。ディキンソンもまた、家族や友人の皆がおこなった信仰告白をしなかったという過去がある(詳細は年譜を参照)。ディキンソンは自分自身への誠実さから、キリスト教の信仰から距離を置く生き方を選択をしたのだろう。このような既存の宗教によらない実存的な在り方を大切にする姿勢は、いかにもディキンソンらしい。でも、そうすることでこころの深いところが傷ついてついてしまうこともまた事実なのだと思う(傷=「容易に埋めることの出来ない空白」くらいの意味です)。
西洋の場合、自立した自我に対する無意識の領域の充足~安定にはキリスト教の信仰がおおきく貢献しているという。修道院から追われる状況は、11~12行目で無防備な状態で自分自身と出会うイメージに対比される。無防備(丸腰)という設定はキリスト教の信仰から引き離されたことと密接に関係しているように思われる。信仰はこころの深い拠り所となって、そのひとを支えてくれる。神さまと共にあることの安心感を与えてくれる。でも、それを拒絶するなら、頼れるのはあとに残されたちっぽけな「わたし」しかいない。
第3連で呈示された「自分自身(自己)」は第4連で「わたし」の背後に隠れていた「わたし」へと展開される。自己は全体性の中心なので、そこには「わたし(自我)」にとっていささか不都合な「わたし」も含まれる。14行目の「驚き(飛び上がるほどの驚き)」は、そのような、本来は意識下に隠されて見てはいけなかった「わたし」を見てしまった(認めざるを得なかった)驚きであることが推測される。その驚きに、死の危険を喚起する暗殺者のイメージが対比されて、「わたし」の驚きが死への恐怖以上のものであることが示される(15~16行目)。
では、驚きの対象として現れる「わたし」の背後に隠された「わたし」とは、どのような「わたし」なのだろう? 具体的な描写に乏しいので、はっきりしたことは言えないけれど、これは「影」(図の青矢印)じゃないかと思う。「影」について河合隼雄の解説をひこう。
影の内容は、簡単にいって、その個人の意識によって生きられなかった反面、その個人が容認しがたいとしている心的内容であり、それは文字どおり、そのひとの暗い影の部分をなしている。われわれの意識は一種の価値体系をもっており、その体系と相容れぬものは無意識下に抑圧しようとする傾向がある。
西洋では自立した自我が求められるので、その反面である「影」との出会いはそのひとの意識体系を脅かすものとして怖れられることがおおいという(この感覚はニュアンスに富む「影」を文化のなかに取り込んできた日本人には実感しにくいものだそうです)。
隠されていた「わたし(影)」への驚き(怖れといってもよいかもしれない)の情動に呼応するかのように、最終連の冒頭(17行目)にいくらか物騒な言葉 Revolver 「リボルバー」が登場する。アメリカの成人男性の象徴そのものであるかのようなリボルバーの登場は、その「影」に拮抗するかのように立ち現れた「アニムス」(女性のなかの男性像)のようでもある。ドアの掛けがねを締めて現実世界の守りを強固にしても、こころの世界の亡霊を阻止することはできない。こころの世界には「わたし(自我)」からは容易に知ることの出来ない領域~死角がいくつもある。詩は最終行(20行目)で Or More と綴られ、その先の不安をかきたてるように終えられる(怖い…)。
作品の内容は、こんなふうにいささか救いのないもの(解決のないもの)だけれど、視点を少しかえて詩のつくりに注目すると、また違った情景が見えてくる。この詩には、ひとつも I 「わたし」が出てこない。作品が「わたし」のこころ(内面)を主題にして歌われるのであれば、そこに「わたし」を投入して語るのが自然ではないだろうか? でも、ディキンソンは巧みに I や me を排除して詩を組み立てている。個としての「わたし」の存在を排除することで、詩はつよく客体化される。つまり、この怖さは、ほら皆さん、怖いでしょ、あなたも同じですよ、というふなメッセージを読み手に投げかける効果を持つ。
この作品をディキンソン個人の精神の不安定さ(躁うつ病や気分障害など)に結びつけた寸評もネットで見かけた。わたしはもう少し大きな視野でこの作品をとらえたい。その背景にディキンソン個人のこころの在り方が深く関係しているとしても、その表現が個を越えて普遍へとたかめられていることの意味を大切にしたい。これは深いところから「わたし」を基礎づけてゆくことの困難さに直面するいまの時代と深く関係した主題なのだと思う。
翻訳ノート
詩は内容の把握がむつかしいところもおおい。どのような訳語が適切なのか、詩全体の構成から時間をかけて考えた。
1~4行 第1連
1行目 to be Haunted は 6行目 Ghost への伏線と考えて「幽霊、亡霊」を組み込まずに「憑かれるのは~」とシンプルな表現とした。4行目 Material Place は、こころの世界に対する物質世界のニュアンスかなと思う。哲学的な方向から「実在の場所」と訳してみた(既存の訳は「現実の場所」と訳してあって、こちらでもよかったかもしれない)。
5~8行 第2連
6行目 Ghost 「幽霊、亡霊、怨霊/霊魂」をどうしよう…… 訳語としてあてられることのおおい「幽霊」だと日本的な幽霊のイメージがかさなってくる。そうするとこの詩にはいまひとつ合わない気もする。むむ、と迷いつつ今回は「亡霊」の訳語を選んでみた。「幽霊」より「亡霊」の方が西洋的な怖さに合うのではないだろうか。
7行目 Host は「(客をもてなす)主人、主催者(国)/(旅館などの)亭主」くらいの意味だけれど、既存の訳は「(もっと冷たい)客」となっている。host には「大勢、群れ、多数」の意味もあるので、そちらからの意訳かなと思うけれど、しっくりこない。第2連から第3連の展開としては Cooler Host → one's a'self となっていて、Host を「客」の方向で訳すと、つぎの one's a'self 「自己、自分自身」へ繋がらない。
Host をキリスト教の信仰から考えてゆくと、わたしたちは神さま(その教え)と共にあるので、こころの世界で出会う Host 「主人」は、神さま(キリスト)であり、その教え(教理)ということになる。その神さまが不在(神さまと共にあることの実感を持てない)ということから Host に Cooler 冷たさのイメージが結合されて、寒々としたこころの在り方が表現されたと理解すると、わたしとしてはしっくりくる。また、先ほどの図からその位置づけを眺めると、Host をこころの世界の中心のイメージでとらえることも出るので、第3連で呈示される one's a'self 「自己、自分自身」を導く。
というようなことを考えつつ適切な訳語を探したのだけれど、これがむつかしい。いろいろ考えてそのまま「ホスト」と訳した。補足として、いま語ったような視点から[こころの在り処]とつけ加えた。
9~12行 第3連
10行目 The Stones a'chase は、石の追跡(追撃)、石に追われる、くらいの意味だけれど、それが具体的にどういう状況なのかよく分からない。石を石像のようなものとすると、修道院のガーゴイルなどに怯えて駆けている情景が思い浮かぶ。でも、石像は動かないのでいまひとつ表現とかみ合わない気もする。しばらく考えて、これって「(修道院から)石もて追われる」みたいなこと? と思った。このようなニュアンスでの理解が可能かよく分からないけれど、個人的な訳ということで石に[投石]と補足した(このあたり参考ということで…)。
11行目 one's a'self 解説で語ったように、自己には「わたし」が知らない「わたし」や「わたし」が認めたくない「わたし」も含まれる。そのような「わたし(自我)」が思っている「わたし」といささか異なる「わたし(自己)」のニュアンスを組み込んで「ありのままの自分自身」と訳してみた。
13~16行 第4連
13行目 Ourself behind ourself は興味深い表現だと思う。これは解説で語ったように「自我」と「影」の関係と理解したい(比喩的に表現すると「表の顔」の後ろに「裏の顔」があるみたいなことです)。その意味では、はじめの Ourself とつぎの ourself は同一ではない(違うからこそ14行目の驚きにつながる)。そのように違ってはいても、どちらも「わたし(わたし自身)」であることにかわりはないので(他の何者かではないので) Ourself ~ ourself というように表現されているのだろう。
それぞれ異なる「わたし」が同列に扱われているということは、「わたし(自我)」からその関係を見ているというより、そこから一歩引いた客観的な視点で「わたし(自我)」と「わたし(影)」の関係を見ているというふうに考えられる(つまり「わたし」の客体化)。そちらの方向から客観的な視点で語られた「わたし」ということで、「 」に入れた「わたし」をあててみた。正確な訳とはいえないけれど、こうすることで意図するところは上手くつたわるのではないだろうか。
17~20行 第5連
19行目 superior 「上位の、高位の/すぐれた」は、第2連の亡霊が外界に結びつけられていることから、外界~物質世界に対する高位 → 精神世界の意味にとらえて「高位[精神世界]の~」と言葉を補足して訳した。
19行目 spectreは、現実世界の Ghost に対するこころの世界の spectre 「幽霊、亡霊/(こころに浮かぶ)怖いもの、怖ろしい幻影」として使い分けられているのかなと思う。日本語訳もそれに倣いたいところだけれど、ちょっとむつかしいようなので、どちらも同じ「亡霊」と訳した。
この作品は極端とも思える精神の過敏さが感じられて、翻訳にあたってはいつもとはちがう疲労を感じた。対比の強調ときれぎれの描写はディキンソン自身の戸惑いのあらわれのようでもある。こちらのこころまでなんだか落ち着かなくなる(どうも苦手だな…)。
- 次回 「水は渇きに教わる」(第13回)
- 前回 「太陽の意匠は」(第11回)
ご案内
- エミリー・ディキンソン 詩と時代~年譜 (目次)
ディキンソン おもな日本語訳