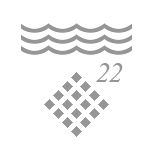ポー 「ユーラルーム 」 Ulalume 《2》 翻訳ノート
エドガー・アラン・ポー「ユーラルーム」《1》 日本語訳 解説 からの つづき(ポーの目次はこちら)。
「ユーラルーム」は語りのトーン(詩に相応しい語りの調子)をつかむのに思いのほか時間がかかった。当初、ポーの他の詩と同じ感覚で訳していたのだけど、どうも上手くいかない(翻訳の波に乗れないといいますか… なぜ?)。今回は、そのあたりのことをいくらか詳細に語ってみたい(興味のある方のみどうぞ…)。
翻訳ノート 1 呪術的な語りの試み
ポーの詩は「音楽的要素」がおおきなウエイトを占めている。そのような英詩を普通に日本語に訳すと(当然のことだけれど)「音楽的要素」はおおきく後退してしまう(ほぼ消失する)。わたしの訳ではポーの詩の持っている「英詩の音楽的要素」を「日本語の語りの調子」に移し替える感覚で作業してきた(英語→日本語の変換の正確さより「調子のよさ」を優先して訳すこともおおかった)。
「ユーラルーム」もそのような方向で訳していたのだけれど、なにかしっくりこない(むむむ…)。これじゃないよなぁ、とは思うのだけれど、なにをどうすればよいのかは分からない(う~ん、困った…)。上手く訳せないのは「ユーラルーム」の世界観に馴染めていないからだろうか? そのようなことを思いつつ、ネットをうろうろしていたときのこと、YouTubeで「ユーラルーム」の朗読を聴いた。その語りはミステリアスな雰囲気というより、どこか呪術を思わせる語りだった。
数日がすぎて、ふと翻訳に取り組んだときのこと、2~3行目
The leaves they were crisped and sere—
The leaves they were withering and sere:
のところを、
葉はかさかさと乾いていて
葉はしおしおと枯れていて
と言葉をそろえるように訳してみた(なにかつかめた気がした…)。呪術的な語りは「同一の調子の繰り返し」(反復)から生まれてくると考えてみよう。この作品では、そのような繰り返しの要素が最も大切ではないのか。ポーお得意のドラマチックな物語性はイメージの背後に後退して、繰り返しの呪術 magic が詩をドライブ(牽引)してゆく。この詩は、そのような仕組み~仕掛けになっているではないか。
加島祥造は解説で、つぎのようなエピソードを紹介している。
ある時、ポーが婦人たちの集まりでこの「ユーラルーム」を朗誦した。すとるひとりの婦人が尋ねた――「ポーさん、どうして私たちに分かる詩をかかないのですか」。そしてポーが答えた――「私はみなさんに分からないようにと書いているのです」。
芸術作品の様式と内容は密接に関係している。詩の主題「ハロウィン」(神話の領域の世界観)は、わたしたちの暮らす世界の物語(近代の物語の世界観)とは遠く隔たっている。ということは、そのための語りもまた、それに相応しいものが求められる。日常の整合性を重視した言葉~物語の構築ではなく、呪術的な語りの技術がわたしたちを近代の自我の領域から神話の領域へと導いてくれる。
よし、これでゆこう、翻訳の方向はきまった! すると、それまでの停滞(ゆきづまり)がうそのように翻訳の作業がすいすいとすすんでいった(詩の翻訳って不思議ですねぇ~)。
翻訳ノート 2 それぞれの日本語訳(参考)
既存の訳(加島祥造訳、阿部保訳)から第1連をご紹介しつつ、わたしの訳の試み(工夫)について語ってみたい。
原詩 Ulalume
Ulalume 1~9行目(第1連)
The skies they were ashen and sober; 1
The leaves they were crisped and sere—A1 2
The leaves they were withering and sere:A2 3
It was night in the lonesome OctoberB1-a 4
Of my most immemorial year:-b 5
It was hard by the dim lake of Auber,B2-a 6
In the misty mid region of Weir:—-b 7
It was down by the dank tarn of Auber,B3-a 8
In the ghoul-haunted woodland of Weir.-b 9
原詩(第1連)は、The leaves ではじまる A1~A2(2~3行目)と、It was からはじまる B1、B2、B3(4~9行目)が同一の調子を持った繰り返しのつくりになっている。語りの調子ということでは、このあたりをどのように訳に取り込んでゆくかが大切になってくると思う。
加島祥造訳
空はいちめん、灰色に曇っていて 1
木々の葉はみんなかさかさに乾いていた――A1 2
どの葉もみんな萎れてかさついていた。A2 3
時刻は夜更け、月は淋しい十月、それもB1-a 4
いちばんぼくの忘れがたいあの年の十月だった。-b 5
場所は暗いオーバー湖のほとりB2-a 6
霧ふかいウエア地方のただなか――-b 7
オーバー湖の暗い水辺のあたりB3-a 8
ウエア地方の幽鬼たちの住む森の中――。-b 9
※ 『対訳 ポー詩集』加島祥造編(岩波文庫)から「ユーラルーム――バラード」第1連より。
加島祥造訳は平易で分かりやすい語りのトーンで訳してある(詩としての味わいのある訳です…)。語りの調子~繰り返しの要素は、
A1 「~ていた――」
A2 「~ていた。」
B1-a
-b
B2-a「~ほとり」
-b 「~ただなか――」
B3-a「~あたり」
-b 「~森の中――。」
となっていて、A1~A2、B2~B3のところが行末の言葉を合わせたつくりになっているようです。
加島祥造の訳は、この他の訳も含めておおよそ平易な語り口で仕上げてある。それが魅力のひとつなのだけど、「ユーラルーム」の場合、平易に語ることを作品の内容をよりよく伝えるための役割と考えると、「内容」と「様式」の関係から、そのかみ合わせがいくらかわるくなるようにも思われる(分かりやすい語り口なのに詩の内容の把握は必ずしも容易くないということになり、分かりやすく語ることで内容の分かりにくさがより浮かび上がってくる)。
また、こちらの訳では、通常の日本語訳では行の並びがひっくりかえってしまうようなところ、B1~3の「a」と「b」がそのままの並びで訳してある(このあたり巧みな処理です)。
参考:詩は1行ごとにイメージが展開してゆくつくり(仕掛け)になっていることがおおい。行の配列は出来るだけ維持して訳したい。でも、英語と日本語は言葉の組み立てが違うので、これがなかなかむつかしい(そのまま訳すと不自然な日本語になりやすい)。わたしの感覚では、英語→日本語の言葉の変換ではなくて、イメージ(内容)の伝達の視点から作業すると上手くゆくような気がしています。
阿部保訳
空は灰色にくすんでいた、 1
木の葉は皺より萎れ――A1 2
木の葉はすがれ萎れていた。A2 3
私のいつとも記憶にない頃のB1-b 4
淋しい十月の夜であった。-a 5
ウイアの霧に朧の中央地帯、B2-b 6
オウバアのほの暗い湖水のほとり――-a 7
ウイアの鬼のうろつくという森林地、B3-b 8
オウバアのじめじめとした山湖のもとであった。-a 9
※ 『ポー詩集』阿部保訳(新潮文庫)から「ユラリウム」第1連より。
阿部保訳は古風な風合いの原詩に誠実な訳といったところだろうか(丁寧なお仕事です)。語りの調子~繰り返しの要素は、
A1 「木の葉は~ 萎れ――」
A2 「木の葉は~ 萎れていた」
B1-b
-a
B2-b「ウイアの~」
-a 「オウバアの~」
B3-b「ウイアの~」
-a 「オウバアの~」
となっていて、A1~A2、B2~B3のところが行頭の言葉を合わせたつくりになっているようです。
4~9行目は、行の並び「a」「b」を反転して訳してある(通常の日本語訳)。加島祥造訳と比べてみると分かると思うけれど、イメージの展開(そのスリリングな雰囲気)としては、 a→b の方がよい気がする。特に9行目 ghoul 「鬼、幽鬼」のイメージは原詩と同じ連の最後の行に置いたほうが「利き」がよいように感じる。
わたしの訳
空はくすんだ灰色で 1
葉はかさかさと乾いていてA1 2
葉はしおしおと枯れていてA2 3
それは寂しい十月の夜だったB1-a 4
遙かな太古からのヴィジョンがあった-b 5
それは暗いオーバー湖だったB2-a 6
ウエア地方は霧が立ちこめていて-b 7
それは湿っぽいオーバー湖の畔だったB3-a 8
ウエア地方の森にはグール[鬼]が棲むという-b 9
既存の訳を参考にさせていただきつつ、繰り返しの持つ呪術の効力を引き出す方向で訳してみた。語りの調子~繰り返しの要素は、
A1 「葉は~ 擬音 ~ていて」
A2 「葉は~ 擬音 ~ていて」
B1-a「それは~ だった」
-b
B2-a「それは~ だった」
-b 「ウエア他方~」
B3-a「それは~ だった」
-b 「ウエア他方~」
というふうになっていて、Aパートは「A2」にも擬音を組み込んで訳した。Bパートは「a」で「それは~ だった」とイメージを提示して「b」で「a」のイメージを展開する組み立てにした。繰り返される各行の「語りの調子」も出来るだけそろえるようにこころを配った。
わたしの訳の場合、語りのトーン~同一の調子の繰り返しを形成するために原詩から離れて変則的な日本語訳になっているところもおおい。あるいは、このような訳にご批判もあろうかと思いますが…… パーソナルな翻訳として、既存の訳にはない新たな試みということでご理解いただければと思います(既存の訳の焼き直しではなくて、新たな要素~工夫を盛り込んだ訳にチャレンジしてゆきたい…)。
(5行目は既存の訳と違う訳になっていますが、この箇所は後ほど語ります)
翻訳ノート 3
《1》の解説の方でおおよそ語ったので、それ以外のところを語ろう。
5行目 immemorial 「(人の記憶、記録にない)遠い昔の、太古からの」をどのように訳すのがよいだろう。既存の訳では「いちばんぼくの忘れがたい年の~」(加島祥造訳)、「私のいつとも記憶にない頃の」(阿部保訳)というふうになっている。この箇所について、加島祥造は解説でつぎのように語っている。
immemorial=im-+memorial. 「記憶できぬ大昔」の意だが、ここでは「忘れがたい」とした。この語をとりあげてT.S.エリオットがポーの用語法をたしなめているのは有名。
ということです…… わたしがここを読んで直感的に思ったのは、この箇所は25行目で提示される「夜=ハロウィン」の伏線となっているのではないかということだった。
「ユーラルーム」は(ポーの考える)ハロウィンのイメージ、ヴィジョンを下敷きにしてつくられている(ハロウィンの世界観に触発されて書かれた作品といってもよいかもしれない)。ハロウィンは西洋のものだけれど、日本にもそれと似た「お盆」がある(ネットで検索してみると他の国にもハロウィンに似た「特別な日」があることが分かります)。
このような「特別な日」をユング的な眼差しで眺めれば、そこに人類に共通した神話~集合的無意識の領域が見えてくる。immemorial を、そのような「個としての記憶」を越えた「神話の領域」が自分自身に宿っていることの示唆と考えてみてはどうたろう(詩的な直感には個人の記憶の枠を越えてアクセスできる領域がある)。わたしの訳では「遙かな太古からのヴィジョンがあった」と訳してみた(積極的な意訳)。
12行目 Psyche は、どのように訳すのがよいだろう。Psyche は、一般には「プシケ、プシュケー」と表記されることがおおい。分かりやすい訳ということなら「プシケ」でいいような気もするけれど、この詩のなかでは「プシケ、プシュケー」の語感はどうも居心地がわるい(おさまりがよくない)。「サイキ」と英語読みの訳とした(既存の訳もおおよそ英語読みの方向で訳してあります)。一般には馴染みのない言葉「サイキ」を補足する意味で、52行目では「美しい魂~サイキ」と言葉を盛って訳した。
(Psyche については、ネットにいろいろと情報があがっているので、興味のある方はそちらをご覧いただけたらと思います)
37行目 Astarte、39行目 Dian → Diana は、一般的な呼び名(イメージしやすい名称)から「アスタルテ(金星)」「ディアナ(月)」とした。
42-43行目は、その理解(解釈)で訳が異なってくる。
She has seen that the tears are not dry on
These cheeks, where the worm never dies,
既存の訳では
彼女は見てきたのさ――涙というものが
死ぬさだめの人間の頬ではけっして乾くことがないとね、
※ 加島祥造訳
この女はうじの絶えない
双頬に涙のかわかないのを見た。
※ 阿部保訳
となっていて…… ふたつの訳でそのニュアンス(意味するところ)はかなり違う。加島祥造訳が人間一般の涙~悲しみの方向で意訳してあるのに対して、阿部保訳では「うじの絶えない~」、つまり、うじ虫のたかる死体(死者)から流れる涙~悲しみのイメージで訳してある。
阿部保訳の方向だと死体のイメージとうじ虫の「絶えない」(never dies)との整合性が気になる。死体はやがて骸骨になるので、そうすると「うじ虫」はいなくなってしまう。加島祥造訳では、そのあたりが「死ぬさだめの人間」と意訳(?)してあって、これは「うじ虫」→「死」からの連想によるものだろうか…… ?
わたしの訳では worm 「ワーム」を、その前の行に置かれている tears 「涙」からの連想~展開と考えてみた。頬をうねうねと伝う涙は worm 「ミミズ」のようでもある。辞書をひいてみると、ことわざとして Even a worm will turn. 「弱虫でも怒れば怖い」というのが載っていた。ということで、worm 「ミミズ」→「頬を流れる涙のイメージ」+「弱虫のイメージ(ひとの弱さ)」ということで「泣き虫」と理解して訳した。
「ユーラルーム」は翻訳の作業に着手してから仕上がるまで半年くらいかかった。長い時間をかけた分、わたしのなかの詩的世界がひろがる方向で、いろいろと得ることのおおい作業~経験になった。
- 次回 第8回につづく(予定)
- 前回 「ユーラルーム」《1》 日本語訳 解説(第7回)
ご案内
- 詩人 エドガー・アラン・ポー (目次)
ポー おもな日本語訳