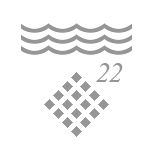ディキンソン 「わたしは〈美しさ〉のために死んだ――けれど」 I died for Beauty — but was scarce
海外の詩の翻訳シリーズ。
エミリー・ディキンソン、第1回「わたしは〈美しさ〉のために死んだ――けれど」 I died for Beauty — but was scarce (449番 1862年)日本語訳と解説(ディキンソンの目次と年譜はこちら)。
※ [ ]は、わたしの補足です。
※ 『対訳 ディキンソン詩集』亀井俊介編(岩波文庫)、『ディキンスン詩集』新倉俊一訳編(思潮社)を翻訳と解説の参考にしました。
日本語訳 わたしは〈美しさ〉のために死んだ――けれど
わたしは〈美しさ〉のために死んだ――けれど
墓に収まり 安らうまもなく
〈本当のこと〉のために死んだひとが
となりの部屋[区画]に横たえられた――
彼は静かに訊ねた「どうして失敗したのだろう?」
「美しさのためよ」とわたしは答えた――
「ぼくは――本当のことのために――このふたつはひとつで――
ぼくたちは兄弟だな」と彼は言った――
だから ある夜に同郷の親戚として出会った――
部屋を隔てて わたしたちは語りあった――
互いの唇に苔が這い寄り――
そして わたしたちの名前を――覆うまで――
原詩 I died for Beauty — but was scarce
I died for Beauty — but was scarce (449)
Emily Dickinson
I died for Beauty — but was scarce
Adjusted in the Tomb
When One who died for Truth was lain
In an adjoining Room —
He questioned softly "Why I failed" ? 5
"For beauty", I replied —
"And I — for Truth — Themself are one —
We Brethren, are", he said —
And so, as Kinsmen, met a Night —
We talked between the Rooms — 10
Until the Moss had reached our lips —
And covered up — our names —
参考:https://en.wikisource.org/wiki/I_died_for_Beauty...
※ 原詩は版によってカンマやダッシュ、大文字、小文字の使い分けなどに違いがある場合があります。こちらでは『対訳 ディキンソン詩集』で使われているテキストThomas H. Johnson: The Poems of Emily Dickinson, 1955に合わせました。
解説 「美しさ」と「本当のこと」の出会う場所
詩は「わたし」の「死」の宣言からはじめられる。「わたし」は美しさのために死んだという。事故や病気ではなく、美しさのために死ぬというのは奇妙なことのようにも思われる(どういうことだろうね?)。
「~のために」というのは「生」のあり方(生の方向性)であり、美しさのために死んだというのは、美しさのために生きたということではないだろうか(美しさのために生きなくて、どうして美しさのために死ぬことが出来ようか…)。美しさのために生きることの奥深くに、美しさのための死が内在されている。そんなふうに考えてみてはどうだろう。詩の作り手であるディキンソンは、詩の語り手の「わたし」をそのような「生の深層~生のなかの死の領域」に導く。
ディキンソンは詩人なので、ここでの「美しさ」を「言葉の美しさ」(詩作)のイメージでとらえてみよう。詩の語り手は「言葉の美しさ」を梯子にして「生のなかの死の領域」に降りてゆく。生のなかの死を見つめることで降りてゆける世界がある。そのようにして「美しさ」が「本当のこと」に出会う。地上(日常)ではそれぞれが独立した事柄に思われたものが、地中では血の繋がった兄弟になる(ここに詩の不思議がある)。ふたつの部屋から互いの声が軽やかに響くとき、「死」の領域にいきいきとした「生」の時間が生まれる。
ふたりの会話は、つきることがないかのように思われた。それでも時は悠々と流れてゆく。墓に刻まれた名前が苔に覆われる頃(あれからどれほどの歳月が過ぎたのだろう…)、自然の「大きな時間」がふたりを包み込む。地中で出会った「美しさ」と「本当のこと」が長い時間のなかで、自然の〈美〉のなかに統合される。詩の結末で描かれる(示唆される)情景はとても美しい。美しさのために死んだものに(美しさのために生きたものに)、自然の〈美〉は静かに応えてくれる。
翻訳ノート
詩の言葉が持っている奥ゆきや広がりをそのまま日本語に転写する感覚で訳してみた。
1~4行 第1連
1行目の Beauty と、2行目の Truth をどのように訳すか、時間をかけて考えた。既存の訳では「美」と「真」(亀井俊介訳)、「美」と「真理」(安藤一郎訳)となっている。わたしの感覚だと、ここでの Beauty を「美」と訳すのはいまひとつしっくりこない。日本語で「美」とすると、その言葉の響きから東洋的な美意識のとのつながりがつよくなるように思われる。そうすると、ここでは少し違う気がする。
日々の暮らしのなかで、東洋と西洋の美意識の違いを意識することはあまりないけれど、じつはずいぶんと違う。わたしの好きな谷崎潤一郎『陰翳礼讃』(中央文庫)から引用しよう。
西洋人は食器などにも銀や鋼鉄やニッケル製のものを用いて、ピカピカ光る様に研きたてるが、われわれはあゝ云う風に光るものを嫌う。われわれの方でも、湯沸かしや、杯や、銚子等に銀製のものを用いることはあるけれども、あゝ云う風に研き立てない。到って表面の光が消えて、時代がつき、黒く焼けて来るのを喜ぶのであって、心得のない下女などが、折角さびの乗って来た銀の器をピカピカに研いたりして、主人に叱られることがあるのは、何処の家庭でも起きる事件である。
「時代がつき」という表現がよいですねぇ~ 一般的に西洋の美は、一点の曇りもなく磨き上げるような「完成」 perfection を目指し、東洋の美はそのなかに傷や汚れ(欠陥や時間の要素)を取り入れる「完全」 completeness を尊ぶ傾向がある(仏像の修復などで、剥落した金箔や表面のくすみはそのままにして時代を経た風合いを大切にするのが東洋的な美意識です)。
詩の冒頭で「わたし」は「美しさのために死んだ」と語る。最高にたかめられた「美しさ」への眼差し(美しさに向かうこころ)が「わたし」を「生」の日常から「死」の非日常へと導く。死=非日常の空間で「わたし」は「美しさ」と兄弟である彼「本当のこと」に出会う。「美しさ」と「本当のこと」は互いのい会話によって分かちがたく結ばれ、長い時間を経て自然(苔に覆われたふたつの墓のイメージ)のなかに統合される。
詩の結末を東洋的な眼差しで見ると、そこには奥深い自然の「美」が立ち現れてくる(わたしにはそのように思われる)。自然の美を、極められて「完成されたもの」というより、すべてを包み込む「完全なもの」として捉えると、ここに「完成」から「完全」にむかうプロセスが見えてくる。わたしたちが詩の結末に東洋的な「美」を見いだすとすれば、そのはじまりは西洋的な「美しさ」とするのがよいのではないだろうか。Beauty を「美しさ」、Truth を「本当のこと」と訳してみた。
1行目 scarce=scarcely は、3行目の When とつながって「…するかしないうちに、…するやいなや」の意味。2行目 Adjusted は墓のなかでの具体的な描写として「安らう」を補足的につけくわえた(墓に収まったらあとは安らかに眠るだけ)。
5~8行 第2連
「わたし」と「彼」の会話のパート。切り詰められたシンプルな会話の雰囲気を大切にして訳してみた(上手く訳せたかな?)。
ダッシュについて少々。ディキンソンの詩では「—」(ダッシュ)がよく使われている。わたしは海外の詩を翻訳するとき、日本語と英語の違いから有効に機能するかたちでダッシュを入れるのがむつかしい場合など、ダッシュを「 」(空白)に置き換えたり、省略することがあった。
ディキンソンの詩で使われているダッシュは、言葉の機能の側面だけではなく、視覚的な効果も大きいように思われる。詩の眺め、見た目の雰囲気を大切にしたいということで、ほぼ原詩に倣ったかたちでダッシュを入れた。
9~12行 第3連
9行目 Kinsmen は「血族(親戚)の男」「同族の人」くらいの意味。ここは第2連 Brethren 「兄弟」からの展開なので「親類」「同族」だといまひとつ言葉の響きが物足りない(弱い)。言葉にいくらか重みをつけて「同郷の親戚」と訳してみた。
9行目 met は「会った」ではなく「出会った」とした(運命に導かれた出会いのイメージ)。11行目、12行目で our が繰り返される。日本語で「わたしたちの~」と繰り返すのもどうかと思ったので11行目の our は「互いの」と訳した。
11~12行目は、1行ずつのイメージを優先して訳すことも出来る。その場合、
だから ある夜に同郷の親戚として出会った――
部屋を隔てて わたしたちは語りあった――
互いの唇に苔が這い寄るまで――
そして わたしたちの名前を――覆った――
というふうになる。日本語の詩として「~まで」と終えるのはいまひとつしっくりこないところもあるので、こちらの訳でもいいかもしれない(詩的イメージからの別訳ということで…)。
ディキンソンの詩を訳していると、こころに不思議な静けさがみちてくる。素敵な時間をありがとう。
- 次回 「わたしは誰でもないひと! あなた 誰?」(第2回)
ご案内
- エミリー・ディキンソン 詩と時代~年譜 (目次)
ディキンソン おもな日本語訳