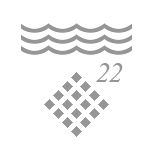ディキンソン 「お別れはしないでおきましょう」 We'll pass without the parting
海外の詩の翻訳シリーズ。
エミリー・ディキンソン、第8回「お別れはしないでおきましょう」 We'll pass without the parting (996番 1865年)日本語訳と解説(ディキンソンの目次と年譜はこちら)。
※ 『ディキンスン詩集』新倉俊一訳・編(思潮社)を翻訳の参考にしました。
日本語訳 お別れはしないでおきましょう
お別れはしないでおきましょう
つらくなるじゃありませんか いりませんよ
不在証明なんて――
思いは募りつつも
離れ離れになることで見えてくるものもありますから
そのように努めて――
向きあったなら 喪失の寂しさではない
死者となります
原詩 We'll pass without the parting
We'll pass without the parting
So to spare
Certificate of Absence ―
Deeming where
I left Her I could find Her 5
If I tried ―
This way, I keep from missing
Those that died.
参考:https://en.wikisource.org/wiki/We'll_pass_without...
※ 原詩は版によってカンマやダッシュ、大文字、小文字の使い分けなどに違いがある場合があります。
解説 それは「わたし」のこころの領域からはじめられる
この詩の内容~翻訳について考えていたとき、大江健三郎の語った言葉がふと思い浮かんだ(詩の言葉はときおり不思議な記憶の導き方をする…)(『新潮』1993年4月号「真暗な宇宙を飛ぶ一冊の書物」より)。
僕は尊敬する作家のお通夜に行ったことはほとんどないんです。(……)家でその人の本を読むことにしている。
大江健三郎の言葉には、故人とのお別れに対してディキンソンと同質の姿勢が感じられた。お通夜という宗教的な儀礼ではなくて、それは「わたし」のこころの領域からはじめられる。詩のエッセンスは、そのあたりにあるのではないだろうか? (どうだろうね?)
3行目 Certificate of Absence 「不在証明(書)」に注目してみたい。これは「存在しないことの証明」ということだけれど、ここでの不在は人間存在の不在というだけではなくて、魂の不在~魂の此岸から彼岸への移行も含まれるように思う(キリスト教文化圏では、ひとの魂は天に召される)。そして、そのような移行による不在を客観的に証明するのは宗教の役割ということになる。詩の語り手は、そのような「お別れ」からは距離を置く態度を示す。
これは見方をかえれば、宗教的な儀礼~信仰では死別の悲しみや寂しさは癒やされないということなのかもしれない。5行目 I could find 「見つけることが出来た」 に象徴されるように、それは「わたし」のこころの積極的な働きによってなされる。故人~死者との直接的で創造的な関係(生死を越えてつづく関係)が「わたし」を悲しみや寂しさから引き上げる契機となる。
参考:このように見てゆくと示唆的な語りの背後に見え隠れしている主題は、ニーチェの「神(キリスト教の神)は死んだ」から実存主義にまでつらなる現代的なものといえるかもしれない(わたしの感慨)。
翻訳ノート
訳詩は途中、約2ヶ月間ほどの中断期間をおいて仕上がった。なぜそのようなことになったのかというと…… (今回はそのあたりことを語ってみよう)
こちらの詩は『ディキンスン詩集』(思潮社)岡隆夫訳を読んで気に入っていた。日本語訳はつぎのようになっている(詩は要約がむつかしいので全文を引用しますね)。
不在証明を持たないためにも
お互い別れを告げずに
別れましょう――
会いたいと思えばまたいつでも別れたところで
お会いできると思いつつ――
亡くなった方々を寂しく思わぬためにも
わたしはいつもこうしています
こなれた訳で(棒ダッシュの扱いがやや気になりますが…)、よい雰囲気に仕上がっています。こちらの日本語訳から入っていったということもあって、当初の翻訳は岡隆夫訳をふまえつつ、行の配列が原詩と同じ並びになるように工夫しながらおこなった(わたしの場合、1行ごとのイメージの展開を大切にしているので、原詩の行の配列を日本語に反映させるスタイルで訳しています)。
短い詩ではあるし、既存の訳もあるので原詩の行の並びに倣った日本語訳はほどなく仕上がった。でも、なにかしっくりこない。これでよいと思える手応えがないといいますか…… あれ? 日本語訳を原詩の行の配列に合わせると日本語と英語の言葉の組み立て方の違いから変則的な訳(おおらかな意訳)になってしまう箇所が出来てくる。そのあたりが上手くいってないのかな? と思いつつ、あれこれ考えてみるもよく分からない(しっくりこない理由が分からない…)。数日粘ったところで作業を中断、半ばあきらめ気分でこの詩の訳を放棄した。気に入っている詩でも上手く訳せないことがある。この詩もそうなのだろうと思うことにした。
それから2ヶ月ほどが経過、ふとこの詩のことを思い出した(どうしてだろうね?)。パソコンで翻訳のファイルを開いてつらつらと眺めた。原詩で5行目のところは、岡隆夫訳では「またいつでも別れたところで/お会いできると思いつつ」と訳してある。この訳をなるほどと思いつつも、そのときのわたしにはもう少し違ったイメージが見えていた。
岡隆夫訳の「別れたところ」は、具体的にはお墓のことだろうか。あるいは記憶のなかの「別れたところ」かもしれない。でも、と思う。5行目に I could find とあり、6行目には I tried とある。それがお墓に会いにゆくことや故人への追憶なら(ただそれだけなら)、その表現はいくらか大仰なものという気もする。ディキンソンであれば、このような場合、もう少し軽やかな表現を好むかもしれない。
わたしはそのとき、こんなことを思った。これは生前には知ることのなかった故人のあらたな姿が見えてくること、そのようなことではないのか? 故人への深い理解や共感によって、それはありありとした実在感のある人物像としてこころのなかに立ち現れくる。それが「見つけることが出来る」ということではないのか? わたしにとっての小さな発見だった。それと同時に、解説で語った大江健三郎の言葉を思い出した(直感の連鎖は面白い)。それが、3行目 Certificate of Absence 「不在証明」の捉え方~理解のきっかけ(ヒント)になった。
Certificate 「証明(書)」というのは、論理的、客観的に明示される事柄なので、わたしと故人というパーソナルな関係から導くことはむつかしい。たとえば、死亡証明書(死亡診断書)であれば病院~医師によって発行される。証明書の発行には客観的な手続き(正統な手続き)が必要になる。では、不在証明(書)を誰が発行するのかというと、解説で語ったようにそれは宗教の役割ということになると思う。つまり、
第1連――宗教の儀礼としてのお別れ~客観的な死者のありよう~その否定。
第2連――こころの領域での創造的な出会い~主観的な死者のありよう~癒やし、救済。
というふうに要約してみてもよいかもしれない。ここまで見えてくると新しい訳への手応えがぐっとたかまってきた(面白くなってきた!)。
さっそく翻訳の作業に取りかかろう。これまで語ってきた詩の背景から浮かび上がってくるイメージを見つめつつ、原詩の言葉のひとつひとつにはそれほどこだわることなく、詩の言葉を立ち上げていった(いつものわたしの手法です)。それぞれの行の細部を試行錯誤しながら検討して、小一時間ほどで新たな訳が仕上がった。今回はこころが納得するものがあった(よかった)。
- 次回 「大切な宝物を手にして――」(第9回)
- 前回 「詩人はランプに火を灯すだけ――」(第7回)
ご案内
- エミリー・ディキンソン 詩と時代~年譜 (目次)
ディキンソン おもな日本語訳