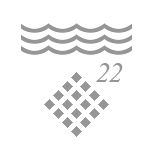T.S.エリオット 「ゲロンチョン」 Gerontion 《1》 日本語訳 解説
海外の詩の翻訳シリーズ。
T.S.エリオット「ゲロンチョン(小さな老人)」 Gerontion (1920)日本語訳と解説(エリオットの詩の目次と年譜はこちら)。
※ 原詩の行の配列をほぼ維持して訳しています。内容の把握がむつかしいところもある詩ですが、分かりやすい日本語の表現をこころがけました。
※ [ ]は、わたしの補足です。
※ 『荒地』岩崎宗治訳(岩波文庫)、『荒地・ゲロンチョン』福田陸太郎 森山泰夫 注・訳(大修館)を翻訳と解説の参考にしました。
日本語訳 ゲロンチョン
おまえには青春もなく老年もない
それは食事のあとでうたた寝をしているようなものだ
双方の夢を見ながら
ここにいる私は乾いた季節の老人
少年の読書につきあいながら雨を待つ
私は灼けつく城門にいたことはないし
なま暖かい雨に打たれながら戦ったこともなく
短剣を手に塩沼で膝までつかり 5
蚋に刺されながら戦ったこともない
私が暮らしているのは朽ちかけた家
窓の敷居にユダヤ人が腰を下ろしている 家主は
アントワープのとある居酒屋で産み落とされ
ブリュッセルでマメをつくり ロンドンで絆創膏を当て一皮むけた 10
夜になると頭上の原野で山羊が咳をする
岩石 苔 ベンケイ草 屑鉄 糞があるところ
女はキッチンに立ち 紅茶をいれる
夕暮れにくしゃみをして くすぶっている火をつつく
私は老人 15
風が空っぽの空間を吹き抜けてゆく鈍い頭
しるしは奇蹟として認められる 「しるしを見ることを願う」
それは言葉のなかの言葉[ロゴス] 言葉は語り得ず
闇の布[産着]に包まれていた 年の甦りに
虎のキリストがやって来た 20
堕落した五月に ハナミズキと栗 花咲くユダ
[ワインが]飲まれ [パンが]分けられ 食べられた
ささやき声のなかの食事[聖餐] シルヴェロ氏は
撫でさする手を持ち リモージュで
隣の部屋を一晩中歩きつづけた 25
ハカガワ氏はティツィアーノの絵の前でお辞儀をする
ド・トルンクィスト婦人は暗い部屋で
蝋燭を移し替える フォン・クルプ嬢は
玄関でドアノブに手を掛け振り返った 空虚なシャトルが
風を織る 私は亡霊を住まわせてはいない 30
すきま風が入ってくる家に暮らす老人
吹きさらしの丘の下
それらを知ってしまった後にどんな赦しがあるのか? さて思案する
歴史はいくつもの狡猾な通路を持っている 作為の回廊や
[見せかけの]出口 野心のささやきがひとを欺き 35
虚栄心が我々を導く さて思案する
我々の注意がおろそかになったとき 彼女[歴史]は授ける
彼女が授けるものには 優れて従順な混乱があり
授けられたことで切望へと飢えさせる ずっと後になって授けられ
それはどうにも信じられないもので それでも信じるなら 40
記憶のなかだけの情熱として再考する あまりに早く授けられ
弱々しい手が受け取り 考慮しないで済ますことも出来るが
拡がってゆく恐ろしさを手が持て余すときまでである 思案する
怯えも勇気も 我々の助けにはならない 残忍な悪は
我々のヒロイズムを父とする 徳は 45
恥知らずの犯罪のうえに 我々にお仕着せられる
これらの涙は憤りが結実した木から揺すられて落ちてくるのだ
新しい年に虎が躍り出る 我々を彼が喰い滅ぼす 最後に思案する
我々は結論に到達しない 私が
借家で[冷たく]硬直しても達しはしない 最後に思案する 50
私は考えもなしに このような見世物をお目にかけたわけではない
こころが乱されたためでも
それが堕落した悪魔たちの仕業ということもない
私はあなたと正直にむきあいたい
私はあなたのこころの在処に歩み寄ったが あなたは離れた 55
恐怖のなかで美しさを失い [異端]審問は恐怖ではなくなり
私はその情熱を失った なぜ持っていなくてはならない?
持ちつづけたとしても純粋なものではありえない
視覚 嗅覚 聴覚 味覚 触覚 を失った
あなたとの親密な交感のために五感をどのように役立てればいい? 60
それらは千のつまらない熟考と共に
凍える錯乱から得られるものを長く引き延ばし
感覚が醒めれば 膜[感覚器官]を興奮させるために
刺激のあるソースを加え 乱立する鏡のなか[荒野]で
様々な有り様を増殖する クモはどのように振る舞うだろう 65
[本来の]作業を止めてしまうのか? コクゾウムシはどうだ
延期するのか? ド・ベイラーシュ フレスカ キャメル婦人が
身震いする「おおぐま座」の軌道を越えて
砕かれた原子になって旋回した カモメが吹き渡る風に逆らって
ベルアイル海峡を飛び ホーン岬を駆ける 70
雪のなかの白い羽 「メキシコ湾流」は力強く流れ
老人は「貿易風」に吹かれ運ばれた
眠たげな片隅へと
その家の間借り人
乾いた季節の乾いた脳の考え 75
原詩 Gerontion
Gerontion
T. S. Eliot
Thou hast nor youth nor age
But as it were an after dinner sleep
Dreaming of both.
Here I am, an old man in a dry month,
Being read to by a boy, waiting for rain.
I was neither at the hot gates
Nor fought in the warm rain
Nor knee deep in the salt marsh, heaving a cutlass, 5
Bitten by flies, fought.
My house is a decayed house,
And the jew squats on the window sill, the owner,
Spawned in some estaminet of Antwerp,
Blistered in Brussels, patched and peeled in London. 10
The goat coughs at night in the field overhead;
Rocks, moss, stonecrop, iron, merds.
The woman keeps the kitchen, makes tea,
Sneezes at evening, poking the peevish gutter.
I an old man, 15
A dull head among windy spaces.
Signs are taken for wonders. "We would see a sign":
The word within a word, unable to speak a word,
Swaddled with darkness. In the juvescence of the year
Came Christ the tiger 20
In depraved May, dogwood and chestnut, flowering Judas,
To be eaten, to be divided, to be drunk
Among whispers; by Mr. Silvero
With caressing hands, at Limoges
Who walked all night in the next room; 25
By Hakagawa, bowing among the Titians;
By Madame de Tornquist, in the dark room
Shifting the candles; Fraulein von Kulp
Who turned in the hall, one hand on the door. Vacant shuttles
Weave the wind. I have no ghosts, 30
An old man in a draughty house
Under a windy knob.
After such knowledge, what forgiveness? Think now
History has many cunning passages, contrived corridors
And issues, deceives with whispering ambitions, 35
Guides us by vanities. Think now
She gives when our attention is distracted
And what she gives, gives with such supple confusions
That the giving famishes the craving. Gives too late
What's not believed in, or if still believed, 40
In memory only, reconsidered passion. Gives too soon
Into weak hands, what's thought can be dispensed with
Till the refusal propagates a fear. Think
Neither fear nor courage saves us. Unnatural vices
Are fathered by our heroism. Virtues 45
Are forced upon us by our impudent crimes.
These tears are shaken from the wrath-bearing tree.
The tiger springs in the new year. Us he devours. Think at last
We have not reached conclusion, when I
Stiffen in a rented house. Think at last 50
I have not made this show purposelessly
And it is not by any concitation
Of the backward devils.
I would meet you upon this honestly.
I that was near your heart was removed therefrom 55
To lose beauty in terror, terror in inquisition.
I have lost my passion: why should I need to keep it
Since what is kept must be adulterated?
I have lost my sight, smell, hearing, taste and touch:
How should I use it for your closer contact? 60
These with a thousand small deliberations
Protract the profit of their chilled delirium,
Excite the membrane, when the sense has cooled,
With pungent sauces, multiply variety
In a wilderness of mirrors. What will the spider do, 65
Suspend its operations, will the weevil
Delay? De Bailhache, Fresca, Mrs. Cammel, whirled
Beyond the circuit of the shuddering Bear
In fractured atoms. Gull against the wind, in the windy straits
Of Belle Isle, or running on the Horn, 70
White feathers in the snow, the Gulf claims,
And an old man driven by the Trades
To a sleepy corner.
Tenants of the house,
Thoughts of a dry brain in a dry season. 75
参考:https://en.wikisource.org/wiki/Gerontion
解説 キリストを巡る物語といまの時代の物語
詩は大きく6つのパートに分けられる。それぞれを見てゆこう…… ということなのだけれど、はじめに「ゲロンチョン」と「死者の埋葬」の関係について語ってみたい。
「ゲロンチョン」と「死者の埋葬」
「ゲロンチョン」は1920年2月、詩集『Ara Vos Prec(我いま汝に請う)』発表された。詩の完成は1919年8月で、エリオットはその年の10月に『荒地』第1部「死者の埋葬」の草稿を仕上げている。創作の順序としては、おおよそ「ゲロンチョン」→「死者の埋葬」という流れになる。
エリオットは当初「ゲロンチョン」を『荒地』のプレリュードとして置くことを考えていて(岩崎宗治の解説)、このふたつの作品は互いによく似たところを持っている。手法の面では即物的なテイストで描写された「いまの時代の物語(情景)」とひとの深層心理につよく働きかけてくるような「神話の領域の物語」とが切り貼りされて同一平面上で展開される。作品が扱う主題もおおよそ似ていているけれど、そこにはいくらかの(ある意味決定的な)違いがある。
「ゲロンチョン」は「いまの時代」におけるキリスト教の信仰への不可能性(困難なさま)を嘆き、一方『荒地』はキリスト教に直接言及していない。『荒地』はキリスト教からは距離を置き、個別の宗教観というよりは、人類とってより普遍的な役割を担う「神話の領域」から「精神の救済」のルートを模索しているように見える。
わたしの感覚では『荒地』の(文学作品としての)成功は個別の宗教から切り離されたところで成立しているところが大きいように思う。エリオットの実人生はキリスト教と深く関係しているので、その「分離」(切り分け)として「ゲロンチョン」のような作品が書かれる必要があったのかもしれない(どうだろうね?)。
そのようなキリスト教の視点から眺めると「ゲロンチョン」という作品は、とても興味深い。また、ある意味なまなましくもある。孤独な老人の「求めたけれど与えられなかった(ついにやって来なかった)」という独白は、エリオット自身のアメリカの地で形成された信仰への複雑な心境の表明のようにも思われる。
参考:エリオットの祖父はユニテリアン派の牧師で、実業家の父も熱心な信者だった。エリオットはニュー・イングランド・ピューリタンの信仰のなかで育ち、後年英国国協会に改宗している。
タイトルと題辞
タイトル「ゲロンチョン」 Gerontion はギリシャ語で「小さな老人」のくらいの意味(geron=老人、-tion=小さい)。
題辞「おまえには青春もなく老年もない~」はシェイクスピア『尺には尺を』 Measure for Measure 第3幕 第1場からの引用。「青春」と「老年」という互いに遠く隔たったものが夢のなかでひとつに融け合う。「おまえ」を「いまの時代」と読み換えることも出来るかもしれない。
1~16行 乾いた季節の老人(1)
1行目、詩の語り手が「乾いた季節(月)の老人」であることが宣言される。この「乾いた」には、キリスト教の信仰が衰退してこころのうるおいを失った「(乾いた)いまの時代」が象徴的に表現されているようにも思われる。
2行目、老人は少年の読書に耳を傾けている。少年が読んでいるのは剣の時代の戦記物だろうか。他にすることもなく時間を持て余した老人が子供向けに書かれた本の読書につきあいながら「雨」(うるおい)を待っている。
3~6行目、老人は少年の読み上げる物語について、自分にはそのような(剣士としての)「経験」はなかったと語る。書物に描かれた物語と現在の状況(いまの時代の物語)とが提示される。このような「物語」の対比は、21~29行目で再び繰り返される(この箇所はそのための伏線と考えることも出来るかも知れない)。
7~14行目、老人の暮らす「家」(集合住宅らしい)について語られる。これは、実際に暮らしている「家」というだけではなく、「家」を「わたしたちの暮らす世界」に見立て描いているような印象を受ける。その視点から眺めると、窓の敷居に腰を下ろしているユダヤ人にイエス・キリストのイメージを見ることも可能かも知れない。
14行目、「くすぶっている火をつつく」は台所の火の調子がよくないということだけれど、(深読みすると)いまの時代のキリスト教の状況を示唆しているようでもある。信仰の火は消えてはいないのだけれど、そのままでは消えてしまいそうで、つついてはみるものの鮮やかに燃え上がりはしない…… そのようなイメージで捉えると、その前の「くしゃみ」の描写ががなんともいえない虚脱感を誘う。
15~16行目、老人の現在の精神状態が提示される。「(風の吹き抜ける空虚な)空間」は、これから展開される情景の器(入れ物)となる。ここから先の語り=ヴィジョンは老人の戯言みたいなものだよということなのかもしれない。
17~20行 神様のしるしはどこに? 虎のキリスト(2)
17行目、sign「しるし」は神の臨在の証のこと。「しるしを見ることを願う」は「マタイ伝」第12章38節からの引用。不信のパリサイ人たちがキリストの教えの正しさの証拠を見せろと迫る。18行目、「言葉のなかの言葉」は「ヨハネ伝」第1章1節「太古[はじめ]に言[ことば]あり、言は神と偕[とも]にあり、言は神なりき」の言葉のことで、意味としては、「(聖書の)言葉のなかの言葉=ロゴス~神」というふうになる。18~19行目、「言葉は語り得ず~ 包まれていた」は、ランスロット・アンドールズがジェイムズ1世のまえでおこなった降誕日の説教からの引用。キリストの誕生が表現されている(以上、岩崎宗治およびの福田陸太郎、森山泰夫の解説からの要約)。
20行目、(満を持して)Christ 「キリスト」(その言葉)が提示され、そこに「虎」のイメージが重ねらる。このパートのおおよその流れとしては、「しるしを見ることを願う」というキリストへの不信からはじまり、言葉と神の関係が語られ、キリストの誕生~獰猛な「虎のキリスト」のイメージへと展開される。この「虎」のイメージは48行目に再び現れ、人々は虎に喰われてしまう。
21~32行 最後の晩餐といまの時代に生きる人たち(3)
21~23行目、聖餐式~最後の晩餐のイメージが透けて見える。聖餐式はキリスト教にとって大切な儀式だけれど、冒頭の「堕落した五月」が象徴するように、それが俗っぽい(いまの時代の)食事の風景にすり替えられる。
24~30行目、信仰を失ったひとたちの(いくらか奇妙にも思われる)日常の情景が描かれる。24行目、リモージュは磁器で有名なフランスの都市。シルヴェロ氏はリモージュでお気に入りの磁器を手に入れ、(うれしさのあまり)それを撫でさすりながら夜を明かしたということだろうか…… あるいは(さらに深読みすると)、夜を徹して祈りが捧げらるというような神様への信仰が磁器という「もの」への欲望に変質したと捉えることも出来るかも知れない(人間ってそんなもの…)。以下、それぞれに個性的な「いまの時代」の人物像が提示される。
29~32行目、老人はそれらの光景を風を織る空虚なシャトルに喩える。いまの時代へのむなしさが滲む(神様の輝かしい物語はいま何処に…)。
33~47行 人間の歴史を俯瞰する 憤りが結実した木と涙(4)
33行目、「それらを知ってしまった後にどんな赦しがあるのか?」については既存の解説から引用しよう。
ここまで知識を得てしまってから、どんな赦しが得られる?
魂のない自分を認識してしまったあと、どんな赦しが期待できようか。(……)「知識」はジョーゼフ・コンラッドの『闇の奥』(1902年)三章で、主人公クルツの死の直前の描写にある「いわば完全な知識を得た至上のその一瞬」という句から暗示されたもの。
※ 岩崎宗治の訳と解説。
こうしたことを知りながら、どんなお赦しが望めましょう。
such knowledge とは、青年時代、神の言葉に接したことを言う。したがって、「福音を知った以上、とんな赦しが得られましょう」の意。この反語は、読者に対して放つかたわら、キリストに対しても問い掛けているものと考えられる。
※ 福田陸太郎、森山泰夫の訳と解説。
ということですが…… (これらの解説も興味深くはあるけれど…)この「知ったこと」は、前のパートを受けての「神の不在」と捉えてみてはどうだろう。24~30行目で描かれた人々は神様への信仰を持たない。ということは当然(神様の)「赦し」とも無関係になる。つまり、いまがそのような神様不在の時代であると認識することで「赦し」の不可能性が表現されているのではないか。そちらの方向から考えてゆくと、それ以降の行へとなめらかにつながってゆくように思われる(参考ということで…)。
34~46行目、信仰のなかの規範(倫理や道徳)を見失った人間の歴史(その顛末)が描かれる。神様への信仰を持たないということは、ひとは自分自身のこころの範囲で物事を考え、判断してゆくことになる。ひとのこころは(神様のように完全なものであるはずもなく)不完全なものなので、結果としてさまざまな痛みがそこに生まれる。
47行目、「憤りが結実した木」については岩崎宗治の解説が興味深い。「この涙は、怒りの実のなる樹から、はふり落とされるのだ」(岩崎宗治訳)
怒りの実のなる樹 エデンにある「知恵の樹」。イヴとアダムは禁断の木の実を食べ、神の怒りを招いた。ヒロイズムの生む悪徳や傲慢の生む罪を嘆く涙は、善悪を知る「知恵の実」が源である。「怒りの実のなる樹」には磔刑の十字架への連想もあるかも知れない。ウィリアム・ブレイクの詩「毒の樹」の中の「朝夕、涙を注ぎ、微笑みの光を当て欺瞞で育てた毒の樹」の連想もある。
なるほど…… わたしがはじめてこの箇所を読んだとき、意味はよく分からなかったけれど(いまも適切に理解できているとは思わないけれど…)、こころがつよく揺さぶられる感覚があった。この箇所は詩の語り手を越えて、〈いま〉という困難な時代を生きるひとりの人間エリオットの静かなこころの叫びを聞いた気がした(この印象はいまもそうです)。
かつて人間に「知恵」を授けた木に、いまは「憤りの実」が結実している。そこから涙がふり落とされる。憤りのなかの悲しみ、悲しみのなかの憤り、これがわたしたちの時代なのだろうか……
48~60行 虎が来ても結論には達しない 信仰を持ちつづけることはむつかしい(5)
48行目、前のパートで提示された「憤り(怒り)」が、我々を喰ってしまう「虎」のイメージとして展開される(おお、なんかすごい…)。この虎を20行目の「虎のキリスト」を引き継いだものとすると(当然そうなるわけだけれど)、ここにキリスト再臨のヴィジョンが見えてくる。ということは、この世界の大掃除がはじまり「千年王国」が…… という展開が予測されるのだけれど、この作品はそちらには向かわない(悲しいくらいにそうはならない…)。
虎に喰われてしまっても、そこから先の展開はない(それでもわたしたちの怠惰な日常はつづいてゆく…)。老人は自分が死ぬときも「結論」には達しないと語る。ここには信仰を望み、でも信仰することへの諦めにも似た失望が感じられる(55行目)。
「わしは、かつてあんたの心のそばにいたのに遠ざけられ」(岩崎宗治訳)
59~60行目、ひとは五感で世界を把握する。キリスト教への信仰もまた五感によって導かれる(荘厳で美しい教会、祈りの歌声、さまざまな儀式、信仰のなかでは風を「神の息吹」として肌で感じたりもする)。でも、現在のキリストはひとの五感で感じることが出来ないほど遠くに去ってしまった(老人にはそのように思われた)。そのようにして信仰から切り離された五感はどこにむかうのだろう? (俗っぽい欲望や快楽へとむかうのだろうか…)
(なぜそのようなことになってしまったのか…… エリオットとキリスト教の信仰については、いろいろと考えたことがあるのだけれど、長くなりそうなので今回は省略します)
61~75行 そして老人は眠たげな片隅へと追いやられた(6)
最終パートは、その意味がトレースされることを拒むかのようにイメージがめまぐるしく展開される。
61~65行目は、わたしたちの五感をあれこれ刺激して利益を得る「欲望の産業」が想起される。既存の解説では老人の内面の描写として捉えられているようだけれど、どうなのだろう? この老人は、その前のパートで「視覚も、匂いも、聴覚も、味も、触覚も、みんななくなってしまった」(岩崎宗治訳)と語る。また、詩の最後では「眠たげな片隅」へと追いやられる。その視点から眺めると、「感覚が冷めると、薄膜を辛いソースで/刺激し」(岩崎宗治訳)などは、この老人のあり方とは相容れないように感じられる(若いひとならいろいろな刺激を求めるだろうけれど…)。これは老人のことではなく、いまの時代に生きるわたしたちのことではないだろうか(どうだろう?)。
65行目(日本語訳は64行目)、乱立する鏡のイメージ(無数の鏡がごたごたと立ち並ぶ広大な迷路)にこころひかれた。鏡は虚像をつくる。信仰から切り離された世界では、すべてが「見せかけ」になってしまうのかも知れない。鏡の世界では「実像~実体」(真実)は姿を現さず「見せかけの××」だけが増殖してゆく。エリオットはこのような現在の状況を悲観的な眼差しで見つめる(わたしにはそのように感じられた)。でも、わたしは(東洋の生まれなので)少し違う印象を持っている。
もともとこの世界ってこんなものじゃないのか? (と思う…)あると思えばない、見ようとするから見えなくなる、目を閉じたら見えてきた…… 幻影に怯えることなく、いまを生きよう。 (生きるってそういうことでしょ? 参考ということで…)
65~67行目、ここで半ば唐突に昆虫(クモとコクゾウムシ)が登場する(はじめて読んだとき ??? となりましたが…)。これは「鏡」に映る人間の variety 「変化、変種」としての「昆虫」ということだろうか? (そちらの方向だと、どこかしらカフカ「変身」を思い浮かべてしまうけれど… 当時、エリオットは「変身」を知っていたのだろうか? ちなみに「変身」が発表されたのは1915年です)。
ここに昆虫を登場させたエリオットの意図はよく分からないのだけれど、「クモはどうするだろう?/動きを中断するのか」(岩崎宗治訳)ということで、本来の仕事が中断されるのか? という意味に理解した。つまり、神様への信仰から考えてゆれば人間の本来の仕事は信仰のなかにあるので、それが中断されたり延期されたりするのか? という問いかけではないだろうか(暫定の理解ということで…)。
67~69行目、詩はさらに(超)展開される。3人のご婦人が砕けた原子になって宇宙を旋回する。岩崎宗治の解説から引用しよう。
死者が原子となって宇宙に投げ出されるイメージは、ジョージ・チャップマン(1559頃-1634)の悲劇『ビュシー・ダンボア』(1607年)から。チャップマンは、罪人は狂った軌道にのせられて無限宇宙に棄てられるという伝説を用いている。
キリスト教の信仰を持たなければ、当然天国もなくなってしまうので、死後は宇宙に廃棄(?)されるということらしい。身震いする(震える)「おおぐま座」については、「熊のオルガスムは九日間つづくという俗説から来たのかもしれない」と解説されている。原子と砕けたご婦人方が見知らぬ惑星(地球)から、びゅ~とやってきたら、「おおぐま座」もびっくりして震えますよね(ちがうかな?)。
69~73行目、ベルアイル海峡は、カナダのラブラドル半島とニューファンドランド島北部のあいだにある海峡。ホーン岬は、南アメリカ最南端の岬。風や潮流、「流れ」のイメージによって世界を巡る詩的情景がすばらしい。
ここで繰り返し提示される地球規模のさまざまな「流れ」は「時流」のメタファーになっているようにも思われる(神様への信仰? いえいえ時代は神様のくびきから自由になる方向にむかっていますよとでもいうように…)。カモメは吹き渡る風に逆らって(つまり信仰を求めて)飛び続け「白」の彼方に去ってゆく(ああ、胸がしめつけられるようなイメージです…)。そして、老人は諦めにも似た境地で雨を待ちながら貿易風にながされるまま「眠たげな片隅」へと追いやられる(なんともいえず切ないですねぇ…)。
74~75行目、
その家の間借り人
乾いた季節の乾いた脳の考え
と詩は終えられる。
仮住まいのようなこの現実世界でかさかさと乾いた思考が行き先も見えないまま頭のなかを巡る。この詩の語り手は老人だけれど、これは年齢というより「現実世界」と「私」(その信仰)との関係から生じる「疲弊の姿」のようにわたしには思われた。そしてそれは当時のエリオット(30代前半)の「こころの姿」にかさなる。
- 次回 「ゲロンチョン」《2》 翻訳ノート (予定)
ご案内