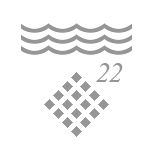T.S.エリオット 「荒地」 死者の埋葬 The Burial of the Dead 《1》 日本語訳 解説
海外の詩の翻訳シリーズ。
T.S.エリオット『荒地』 The Waste Land (1922)から「死者の埋葬」 The Burial of the Dead 日本語訳と解説(『荒地』日本語訳だけをまとめて読みたい方はこちら)。
※ [ ]は、わたしの補足です。「 」は原詩の表記に従いました。
※ 『荒地』岩崎宗治訳(岩波文庫)、『荒地・ゲロンチョン』福田陸太郎 森山泰夫 注・訳(大修館)を翻訳と解説の参考にしました。
日本語訳 死者の埋葬
I. 死者の埋葬
四月はいちばん残酷な月だ
ライラックを死の土地から育てあげ
記憶と願望を乱雑にもつれあわせ
ぼんやりした〈根〉を春の雨で[不穏に]活気づける
冬はあたたかに装ってくれた 降る雪が 5
大地をおおい 記憶を曖昧に隠してくれた
球根は乾いていて ささやかな人生を享受した
夏には驚きがあった シュタルンベルク湖の方角から
通り雨がやって来た 私たちは柱廊の下で雨宿りした
それから日が差すのを待って ホーフガルテンで 10
小一時間 コーヒーを飲みながら会話を楽しんだ
ロシア人ではなくて リトアニア生まれのドイツ人です
わたしたちは子供でした 大公のお屋敷に泊まっていたとき
従兄が わたしをソリ遊びに連れ出したけれど
怖くて怯えてしまった 彼の声が響いた マリイ 15
マリイ しっかりつかまっているんだ それから滑り降りた
山の自然のなかでは くつろいだ気分になれます
夜はいつも本を読みます 冬は南へゆくんです
胸を締めつけてくる この〈根〉はなんだ? どんな枝が
石ころのガラクタから育つというのか? 人間の子よ 20
君には想像できないし 語れないだろう 君が見知っているのは
壊れた不完全な〈像〉の集積にすぎない そこでは太陽が容赦なく輝き
日差しを避ける朽ち木の影もなく コオロギの鳴き声が安堵を
もたらしもしない 乾いた石に水の気配はない
たったひとつ 赤い岩のもとに影がある 25
(赤い岩の影に入ってごらんなさい)
まだ見たことのないものを 君に見せてあげよう
それは朝の日差しのなかで君の後ろについてくる影ではなくて
夕暮れの長く延びて君を迎えてくれる影でもない
君を恐怖に突き落とす ひとつかみの〈塵〉を見せてあげよう 30
さわやかに風が吹き抜けてゆく
故郷へ
アイルランドの少女よ 君は
いまどこにいますか?
「一年前 あなたが最初に下さったのはヒヤシンスでしたね 35
「あのとき以来 ヒヤシンス嬢と呼ばれています」
ヒヤシンス園から ふたりで遅く帰ってきたとき
君は髪を濡らして 両手いっぱいに花を抱いていた 私はなにも
言えなかった 視界はかすんしまって 生きているのか
死んでいるのか なにも分からず ただ静けさのなかで 40
こころのなかの淡く光る一点を見つめていた
鈍色の空虚な海よ
千里眼で有名なマダム・ソソストリスは
あいにく風邪をひいていたのだが
魔術的なタロット占いでは ヨーロッパで屈指の 45
腕前だという これよ と彼女は言った
これがあなたのカード 溺れ死んだフェニキア人の水夫
(この真珠が彼の瞳よ ごらんなさい!)
これはベラドンナ 美しい岩窟の淑女
彼女はさまざなに境遇をあらわします 50
これは三本の棒[ステイブ]と男 これは運命の輪
そしてこれは片眼の商人 ここのカードは
空白になっていますね これは彼が背負って運ぶなにかですが
私には禁じられた領域です 吊し人のカードは
出ていません 水死の心配があります 気をつけて 55
群衆が見えます 人々が輪になって歩いている
ありがとう もしエクィトーン婦人にお会いになったら
ホロスコープはこちらからお持ちしますとお伝え下さい
この頃は なにかと注意深くしないといけません
空想の都市 60
冬の夜明け 朝霧はブラウンに染まっていた
ロンドン橋の上にたくさんの人たちの流れがあった
〈死〉がなしたことの大きさを思わずにはいられなかった
彼らはときおり短く溜め息をついて
動きのない眼差しは 終始 足もとを見つめていた 65
その流れは坂道を上り ウィリアム通りを下った
サンタ・マリア・ウルノス教会は九時の鐘を打ち鳴らすと
それを最後に沈黙した
私は知人をみつけて呼び止めた 「ステットソン!
「君とはミュラエの海戦で一緒だったね! 70
「君は昨年 死体を庭に植えたそうじゃないか
「それは芽を出したかい? それは今年 花を咲かすのかい?
「それとも 突然の霜にやられてしまったかい?
「犬を近づけるんじゃないぞ 人にとって友達でもな
「その爪で また掘りおこしてしまうぞ! 75
「君! 偽善の読者! 同胞 兄弟よ!」
原詩 The Burial of the Dead
The Waste Land
T. S. Eliot
I. The Burial of the Dead
APRIL is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.
Winter kept us warm, covering 5
Earth in forgetful snow, feeding
A little life with dried tubers.
Summer surprised us, coming over the Starnbergersee
With a shower of rain; we stopped in the colonnade,
And went on in sunlight, into the Hofgarten, 10
And drank coffee, and talked for an hour.
Bin gar keine Russin, stamm' aus Litauen, echt deutsch.
And when we were children, staying at the archduke's,
My cousin's, he took me out on a sled,
And I was frightened. He said, Marie, 15
Marie, hold on tight. And down we went.
In the mountains, there you feel free.
I read, much of the night, and go south in the winter.
What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man, 20
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water. Only
There is shadow under this red rock, 25
(Come in under the shadow of this red rock),
And I will show you something different from either
Your shadow at morning striding behind you
Or your shadow at evening rising to meet you;
I will show you fear in a handful of dust. 30
Frisch weht der Wind
Der Heimat zu,
Mein Irisch Kind,
Wo weilest du?
"You gave me hyacinths first a year ago; 35
"They called me the hyacinth girl."
—Yet when we came back, late, from the Hyacinth garden,
Your arms full, and your hair wet, I could not
Speak, and my eyes failed, I was neither
Living nor dead, and I knew nothing, 40
Looking into the heart of light, the silence.
Od' und leer das Meer.
Madame Sosostris, famous clairvoyante,
Had a bad cold, nevertheless
Is known to be the wisest woman in Europe, 45
With a wicked pack of cards. Here, said she,
Is your card, the drowned Phoenician Sailor,
(Those are pearls that were his eyes. Look!)
Here is Belladonna, the Lady of the Rocks,
The lady of situations. 50
Here is the man with three staves, and here the Wheel,
And here is the one-eyed merchant, and this card,
Which is blank, is something he carries on his back,
Which I am forbidden to see. I do not find
The Hanged Man. Fear death by water. 55
I see crowds of people, walking round in a ring.
Thank you. If you see dear Mrs. Equitone,
Tell her I bring the horoscope myself:
One must be so careful these days.
Unreal City, 60
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.
Sighs, short and infrequent, were exhaled,
And each man fixed his eyes before his feet. 65
Flowed up the hill and down King William Street,
To where Saint Mary Woolnoth kept the hours
With a dead sound on the final stroke of nine.
There I saw one I knew, and stopped him, crying "Stetson!
"You who were with me in the ships at Mylae! 70
"That corpse you planted last year in your garden,
"Has it begun to sprout? Will it bloom this year?
"Or has the sudden frost disturbed its bed?
"Oh keep the Dog far hence, that's friend to men,
"Or with his nails he'll dig it up again! 75
"You! hypocrite lecteur!—mon semblable,—mon frère!"
参考:https://en.wikisource.org/wiki/The_Waste_Land
解説 失われた恋人から時代のなかの死者たちへ
作品にちりばめられた(興味深い)イメージがどのように組み立てられ、展開されているのかを語ってみたい(内容の詳細は「翻訳ノート」で語る予定にしています)。
失われた恋人の行方
「死者の埋葬」は、「四月」「ライラック」「記憶」「鈍い根」(意識下の隠喩)のイメージからはじめられる。これらはすべて1行目の「残酷」に結びつく。四月はよい季節だし、ライラックの花も美しいのに、なぜそれらは「私」にとって残酷なのだろう? (どうしてだろうね?)
春のひとつ前の季節、冬のパート(5~7行目)の forgetful snow 「忘れっぽい雪」に注目しよう。これは春のパート(1~4行目)の「記憶」と呼応しているように思われる。つまり、「私」にとっての「残酷」の原因(その一端)は「記憶」にあることが推察される(春に思い出される記憶がこころを穏やかではない状態にさせている)。では「私」にとって思い出したくない「記憶」とは、どのようなものだろう。
冬のパートの次は(さらに時間をさかのぼって)夏の情景が展開される。夏には通り雨の驚きがあったと「私」は語る(8~9行目)。これは恋人とのデートの場面だろうか。ふたりはホーフガルテンでコーヒーを飲みながら会話を交わす。マリイが子供の頃の思い出を「私」に話す(13~16行目)。プライベートな話題を気さくに話す彼女の雰囲気から、ふたりのうち解けた関係が想像される。
夏の情景には恋人たちのいきいきとした雰囲気がある。その後、このふたりはどうなったのだろう? このふたりがいまも恋人同士で、その後も楽しいデートをかさねていると推測するのは、ちょっと無理がある。マリイのような(素敵な)女性と恋仲であれば、四月が「残酷」ということは考えにくい。詩の情景は、春、冬、夏と時間をさかのぼるように展開されていて秋が欠落している(秋になにかあったのだろうかとつい想像してしまうけれど…)。「私」は、たぶん秋に恋人を失ってしまったのだろう。
失われた恋人の記憶が「私」のこころを穏やかではない状態にさせる。あの頃の記憶(夏の思い出)と願望(それは叶う望みがない)が、四月に花を咲かすライラックの情景と二重写しになって「私」のこころをつらくさせる(不安定にさせる)。きらきらと輝いていたあの頃、「夏の思い出」が「私」の胸をしめつける。でも、この胸の痛みは、それだけなのだろうか? (なにか違うような気がする…)
What are the roots that clutch 「締めつける(こころをぐいとつかむ)根=根源はなんだ?」と「私」は自問する(19行目)。stony rubbish 「石ころのガラクタ」(20行目)のように荒廃したこころ(精神状態)から、どのような人生が可能というのか? (う~ん、そのように考えるとつらいものがありますね…)
ここで語り手が交代する(20行目)。Son of man 「人間の子よ」と人間を超えた立場の方(神様クラスの方?)が語りはじめる(この語り手の交代を見逃すと詩が分からなくなるので注意)。「君」が知っているのは(見ているのは)、broken images 「壊れたイメージ」(22行目)にすぎないという。
broken images をどのように理解すればよいだろう…… broken images を「壊れた偶像」の方向で訳したものもあるけれど、それはどうも違うような気がする(詳細は「翻訳ノート」で語る予定にしいます)。第2連が第1連を引き継いで展開されているとすれば、ここでの images は「夏の思い出~失われた恋人」を起点にして考えてゆくのがよいのではないか。
「夏の思い出」の描写は明るく無邪気で、それでいて(だからこそ)妙に切ない印象が残る。down we went 「滑り降りた」や go south in the winter 「冬は南へゆくんです」には、去ってゆく恋人のイメージが重ねられているようにも思われる。では、実際の夏はどのようなものだったのだろう。「私」は、恋人との「夏の思い出」をありのまま、(真実として)思い描き、語ることが出来るだろうか? たぶん出来ないだろう……
なぜなら、それは「失われた恋人」と共に思い描かれる情景であり、そこから「喪失の感情」だけを切り離して夏の情景を思い描くこと(語ること)は出来ないのだから。つまり「私」の語る「夏の情景」は「喪失の感情」によって歪められている。それを「真実」の側からみれば、それらのイメージは壊れている(損なわれている)と言えるのではないか。
「石ころのガラクタ」の情景は「喪失により傷ついたこころの心象風景」であり、そのようなこころのあり方のフィルターを通して「私」は過去を回想し、世界を眺めている(そして苦しんでいる)。認識や記憶はそのときの心理状態に大きく影響を受ける(失意や悲しみのなかでは同一の情景がそれまでとは違って見える)。ひとのこころはそのように不完全なものであり、ここでの broken images とは、そのような(神様から切り離された)「生身の人間」が思い描く不完全なイメージを指しているのではないだろうか(どうだろう…)。
この箇所の理解は、わたしにはむつかしいのだけど、神様への信仰を失った人間(近代)は「完全なイメージ」=「真実」(絶対的な真実)を知ることは出来ない。なぜなら、それが「真実」であることを保証出来るのは唯一神様しかいないのだから…… (神様なら一点の曇りもなく世界を見渡せるだろう)当然のこととして、「真実」から導かれる「調和の世界」(平和で満たされた世界~楽園)にも到達しない。
あれこれ思い悩んでみても、こころはつらくなるばかり。得体の知れない〈根〉が「私」の胸を締めつける。結局、20世紀に暮らす人間(近代)に与えられたのは、太陽が容赦なく照りつける不毛の土地だった(これを神様の「調和の世界」に対する人間の「荒廃した世界」と考えることも出来るかもしれない)。そこに安らぎはなく、当然のように〈水〉もない。こころのつらさ(渇き)はつのるばかり(ああ、つのるばかり…)。
語り手は「君」がまだ見たことのない怖ろしいものを見せてあげようと語る。それはひとつかみの dust 「塵」(または「灰」)だった(30行目)。「塵」は死を暗示する(さらに遠くを眺めれば、アダムがそれによってつくられた「塵=土」のイメージを見ることも可能かも知れない)。「失われた恋人」に「死」のイメージが引き合わされる。
(このあたり、近代に暮らす人々の救いのない幻滅が見え隠れする…)
人間を超えた立場の方の語りは、ここでぷつりと終わり、「生」と「死」ふたつの領域の関係を象徴するかのように『トリスタンとイゾルデ』の歌が引用される(31~34行目)。故郷にむかえばアイルランドの少女にはもう会えない、アイルランドの少女に会いに戻れば故郷には帰れない…… (此岸と彼岸は互いに遠く隔たっている…)
でも、詩の世界ではいくらか不思議なことが起きる。hyacinth girl 「ヒヤシンス嬢」のイメージ(35~41行目)は、この作品のなかでもっとも切ないものかもしれない。「一年前 あなたが最初に下さったのは~ あのとき以来 ヒヤシンス嬢と呼ばれています」と、彼女は語る(この場面を、ふ~ん、そうなんだと思って読みすすたあなた、詩のおいしいところを見逃してますよ、よく考えてみて!)。
「一年前 あなたが~」ということは、この台詞が語られたのは、その1年後ということになる。ヒヤシンスは春に開花するので、時系列的には今年の春に彼女(ヒヤシンス嬢)が「私」に語ったというわけだけれど…… うん? それを認めてしまうと冒頭の「失われた恋人」のイメージと矛盾してこないか?
今年の春に(ライラックが花を咲かせる頃に)、現実の出来事として「私」と「ヒヤシンス嬢」が出会うことは考えられない。では、この彼女はいったい何者? Hyacinth garden 「ヒヤシンス園」は「私」のこころのなかの「失われた恋人」の住まう場所であり、それはわたしたちが「天国」と呼んでいる場所と同質のものではないだろうか(信仰を持たない「私」は宗教が描く「天国」を持たない)。
「こちらの世界」(此岸)ではなく「失われたものたちの世界」(彼岸)でふたりは再会する。このとき「私」は「失われたものたち」(死者)の領域に半分沈んでいる。「私」は「生きているのか」「死んでいるのか」分からなかったと語る(39~40行目)。現実の記憶が「死者」によって浸食されてゆく(こころを病んだひとにありがちな精神状態…)。『トリスタンとイゾルデ』から再び引用がおこなわれて(42行目)、「ヒヤシンス嬢」のパートが終わる。
時代のなかの無数の死者たち
ここまでの展開を「起」「承」とすると、次のパートは「転」になる。マダム・ソソストリスがタロットカードで「私」を占う(43~59行目)。この占いで語られるあれやこれやは「死者の埋葬」だけではなく『荒地』全体の「予言」(伏線)になっている。占いは非科学的なものではあるけれど、理性(知的な推測、現実の領域)と非理性(オカルト的空想、神話の領域)が同一平面上で展開されることに注目しておこう。
最終連(60~76行目)は、起承転結の「結」のパートになる。場面はさらに大きく展開される(死者を巡るイメージが加速して、さらにその深みへと下りてゆく)。冒頭(60行目)で、ここが Unreal City 「空想の都市」(非現実の都市)であることが宣言される。「私」の空想=内的世界の都市は、まるで死んだように生気のないひとたちであふれていた。「死者の行進」を思わせる、このひとたちはいったいなに?
エリオットの原注によると、63~64行目はダンテ『神曲』から「地獄編」を引用したものだという。岩崎宗治は解説で、このような都市の情景(ロンドンの金融街シティの人々)について「現代人は『本当に生きたことがない人たち』だということ」と語っている。つまり「現代人批判」なわけだけれど……
わたしは、そのようには考えない。そのような理解は、これまでみてきた詩の全体の流れから遊離してしまう(詩のタイトルが「死者の埋葬」となっていることをいまいちど確認しておこう)。これらの「生気のないひとたち」は「私」の深層心理に沈んでいた「無数の死者」が金融街シティの情景に投影されたもと考えるのが妥当ではないだろうか(大切な指摘)。
この「無数の死者」(死者の群像)こそが「私」のこころをつらく、落ち着かなくさせていた〈根〉の正体なのだろう(信仰を持たない「私」は、ダンテが『神曲』で描いて見せたような「天国」や「地獄」のヴィジョンを持つことがない、その場所は「現実のどこかの場所」によって代替される)。
意識下の「無数の死者」を理解するには、歴史的な背景を知る必要がある(丁寧に語ると長くなるので手短に語ってみよう)。
『荒地』は1922年に発表されていて、第I部の草稿は1919年10月に執筆されている。その前年(1914~1918年)、世界は第一次世界大戦を経験している。これは人類が初めて経験する世界規模の戦争であり、おおくの命が失われることになった(ネットで調べてみると戦死者の総数は1600万人くらいだった、めまいのするような巨大な数字です…)。
近代以前、神様への信仰がまぶしく輝いていた頃、死者には「天国」(あるいはそれは「地獄」かもしれないけれど)が用意されていた。わたしたちは、ごく当たり前のように「死者」を「天国」に送ることが出来た(さようなら、天国で安らかにお眠り下さい…)。でも近代以降、神様の輝きは失われ、それと同時に死者のための「天国」も見せかけのものになっていった(そのような場所をこころの底から信じることは出来なくなった)。宗教の信仰ではなく、このちっぽけなこころで、わたしたちは「死者」とむきあわなくてはならない。
「人間的な愛」(人類愛)は産業革命以降の都市から生まれたものだけれど、それを「死者」との関係から眺めれば、すべての「死者」が個人との繋がりを持つようになる(なぜならどの死者も同じ人類なのだから…)。無関係なひとの死だからといって無視することはもう出来ない。これはつまり、第一次世界大戦の「死者」(悲劇)を、このちっぽけなこころで引き受けなくてはならないことを意味する(すぐれた作家の資質のひとつに「時代を引き受ける」ということがある、エリオットもまたそうだったのだろう)。
教会の鐘は、九時を最後に沈黙する(67~68行目)。死者たちは「未来の時間」を持つことがない(死者の永遠性)。死者たちを前に沈黙する教会は、その役割(救済)を放棄してしまったかのようでもある…… 死者たちは、この場所の他にゆく術を知らない。死者たちはいつまでも「私」のこころのなかに、「空想の都市」にとどまりつづけている……
「私」はその流れのなかに知人をみつけて呼び止める。彼、ステットソンとは「ミュラエの海戦」を共に戦った戦友らしい(紀元前におこなわれた海戦に第一次世界大戦のイメージがかさねられる)。そこではじめて corpse 「死体」というな生々しい言葉=イメージが登場する。それまでの「死」(死者、喪失)を巡るイメージが、戦争に結びつけられた「死体」という具体的な「姿」として、わたしたちの前に提示される。
「死体」は(信仰と結びついた)「墓地」ではなく、ひとの生活の場である「庭」に埋められる。それは霜にやられたり、犬に掘り返されたりしなければ、やがて芽を出し、花を咲かせるという。生々しい死体が、美しい花、ひとのこころを苦しめることのないおだやかな「死の姿」へと転換される可能性が示唆される(でも、それが上手くいくかどうかは分からない、可能性にとどまるところがこの詩の限界であり、それは当時のエリオットの限界でもあったのだろう)。
花のイメージは、冒頭のライラックのイメージと結びつき、ここにひとつの円環が閉じる。来年の四月、ライラックが花咲く頃、「私」はそこになにを見て、なにを思うのだろう(あなたのこころは、いま穏やかですか?)。
詩は「君! 偽善の読者! 同胞 兄弟よ!」(最終行)と終えられる(ボードレール『悪の華』より「序歌――読者に」からの引用)。これはエリオットから読者への呼びかけでもあるという(岩崎宗治の解説)。わたしたち読者は「時代のなかの死者」とどのように向き合えばよいだろう。それは「死者」の側からみれば「偽善」(不誠実)と映るものかも知れない。
意識の上では気にしていないつもりでも、信仰=天国を持たないわたしたちのこころは「無数の死者」と無関係ではいられない(死者は静かにわたしたちのこころに入り込んでくる…)。「同胞 兄弟よ!」とエリオットの呼びかけに死者たちの声が重なり響く!
ご案内