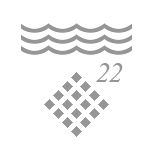レエン・コオト
長椅子の上の眠りは温かなチョコレートのように溶けて、わたしたちの夜が来る。そうだ! 大切な約束があった。
いくつもの小さな矩形に仕切られた陳列棚をじっと見つめた。なにが収められているのかは暗くてよく分からない。墨色のヴェールをまとった不定形の存在の気配たち。閉店後の百貨店は闇の見本市のようだね。
風呂敷包みをさげて、お届け物に出かけよう。ご注文の品は英国製のレインコート。生地のあいだにゴムをはさんだ完全防水仕様。止まっているエスカレーターを歩いて下りる。通用口から外に出た。手帳を開いてお届け先の確認。タクシーを拾って指定されたホテルにむかった。
交差点で信号待ちをしていると隣の車線に黒塗りタクシーが停まった。後部座席に乗車していたのは緑色のレインコートを着た男だった。膝のうえの風呂敷包みが乾いた音を立てた。レインコート同士、お互いに通じあうものがあるのだろうか。
ご機嫌いかが?
そういえば、レインコートが繰り返し出てくる小説があったな。有名な小説のはずだけれど…… そうそう、レインコートじゃない、レエン・コオトだ。タクシーはタクシイで、カフェはカッフェ。
昼間に幽霊が出るお屋敷だった。それも天気のよい日ではなくて、雨降りの日を好んで現れるという。
「雨のふる日に濡れに来るんじゃないか?」
「御常談で。……しかしレエン・コオトを着た幽霊だって云うんです」
ご冗談で。
やがて主人公の視界に半透明の歯車が現れ、回りはじめる。ああ、思い出した「歯車」だ。作者は芥川龍之介。読んだのは、たぶん十三、四歳頃。どこか人工的な匂いのする強迫的聯想。精神の摩滅がこちらにまで伝染しそうで気味が悪かった。
「まだ体の具合は悪いの?」
「やっぱり薬ばかり嚥んでいる。催眠薬だけでも大変だよ。ヴェロナァル、ノイロナァル、トリオナァル、ヌマアル……」
作家Aは結婚披露式に呼ばれたホテルに部屋をとって小説を執筆していた。窓にカアテンをおろして、昼間でも電燈をともしたまま鼹鼠[もぐらもち]のように小説を書きつづけた。そのとき彼が執筆していたのは……
物語の舞台は昭和初期の由緒ある湯治場。神隠しの伝説をなぞるように子供たちが消えていった。神社の境内に落ちていた一冊のノート。水性のインクで書かれた名前の文字は滲んでいて判読できない。表紙の裏のポケットに謎のメモ書きが入っていた。
アラベンタ ハナゴンタ アナゲンタ
そしてサーカスがやってくる。軽業師の華麗な曲芸。熊の玉乗り。ライオンがたてがみをなびかせて火の輪をくぐり抜けた。ピエロが笑いを誘い、子象が愛嬌をふりまく。花形はなんといっても空中ブランコ。フィナーレは団員全員の合唱。顔を白塗りにした子供たちが手をつなぎ輪になって童謡を歌う。
むかし人さらいは
子供たちを探したが
いまは子供たちが
人さらいを探している
「ムンクの「叫び」っていう絵、知っているかな、あの感じ。橋のうえで耳を覆って絶叫している、緑色の男、背景はただひたすらに赤……」
翌日は激しい雷雨だった。廃駅の構内でレエン・コオトを着た探偵Bの死体が発見された。死因は不明。迷宮小説の名作だと思うな。あれ? なにか間違えている? こまかいことは気にしない。おおらかな人間になるのが人生の目標です。
「どうもした訣ではないのですけれどもね、唯何だかお父さんが死んでしまいそうな気がしたものですから」
ホテルのカッフェに先生の姿はなかった。仕方ない。先生の不在は半ば予想されていたことだった。でも、そのことに気がつかないふりをした。手帳のページを見返しているうちに言葉に出来ない悲しみがこみあげてきた。
これからどうすればいい? ……熱いココアを飲もう。
詩作メモ
街の小さな本屋さんで文庫本の棚を眺めていると芥川龍之介と安部公房の作品が並べて置かれていることがよくある(これもなにかのご縁で…)。
芥川龍之介「歯車」と安部公房『カンガルー・ノート』、このふたつの作品はまったく似ていない。でも、どこか遠くで呼応しあっている気がしている。どちらともが、ありふれた日常の情景からはじめられ、日常では起こりえない(体験することのない)恐怖=怯えで終えられる。
ご案内