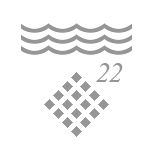ポー 「湖、……に」 The Lake — To ——
海外の詩の翻訳シリーズ。
エドガー・アラン・ポー、第5回「湖、……に」 The Lake ― To ―― (1827)日本語訳と解説(ポーの目次はこちら)。
1.日本語訳 2.原詩 3.解説 4.翻訳ノート
5.加島祥造の解説について
※ ポーの詩のエッセンスが日本語の詩として上手く伝わるように表現を工夫しながら、自由なイメージで訳しています。解説、翻訳ノートとあわせてお読み頂けたらと思います。
※ 『対訳 ポー詩集』加島祥造編(岩波文庫)を翻訳と解説の参考にしました。
日本語訳 湖、……に
ぼくがまだ少年の面影を残していた頃
世界は広々とした遊び場で そこに
とっておきの愛すべき場所があったんだ――
その美しい眺めはもの寂しい心象風景のようで
荒涼とした湖は他に訪れるひともなく
背の高い松と黒々とした岩に囲まれていた
でも 夜のとばりが降りてくると
あたりはみるみる闇に覆われてゆく
怪しい風が吹きはじめて 耳を澄ますと
夜を舞う風のメロディがかすかに聞こえる――
そして――ああ そして 孤独な湖がやって来る
ぼくのこころに怖さが満ちてゆく
怖さは身のすくむ恐怖ではなくて
全身がぞくぞくするような ふるえる悦びだった
この素晴らしい体験=感覚を言葉にして
教えてあげることは宝石と引き替えでも出来ないな――
それが愛であっても――きみの愛でもね
〈死〉は致死性の毒を含んだ波に潜み
入江に沿って不気味な墓が立ち並んでいる
ここは ひとのこころをなぐさめへと導いてくれる
お一人さま限定の空想空間――
孤独な魂がつくりだす鮮やかなヴィジョンは
暗さに沈む湖に見つけたエデンだった
原詩 The Lake ― To ――
The Lake ― To ――
Edgar Allan Poe
In spring of youth it was my lot
To haunt of the wide world a spot
The which I could not love the less—
So lovely was the loneliness
Of a wild lake, with black rock bound, 5
And the tall pines that towered around.
But when the Night had thrown her pall
Upon that spot, as upon all,
And the mystic wind went by
Murmuring in melody— 10
Then—ah then I would awake
To the terror of the lone lake.
Yet that terror was not fright,
But a tremulous delight—
A feeling not the jewelled mine 15
Could teach or bribe me to define—
Nor Love—although the Love were thine.
Death was in that poisonous wave,
And in its gulf a fitting grave
For him who thence could solace bring 20
To his lone imagining—
Whose solitary soul could make
An Eden of that dim lake.
参考:https://en.wikisource.org/wiki/The_Lake — To ——
※ 原詩は版によってカンマやダッシュ、字下げなどに違いがある場合があります。こちらでは『対訳 ポー詩集』で使われているテキスト Thomas Ollive Mabbott: Collected Works of Edgar Allan Poe, Volume I, Poems, 1969 に合わせました。
簡単な解説
詩で描かれる湖は「昼」と「夜」、ふたつの顔を持っている。昼から夜への移行によって「自然の湖」 wild lake が「孤独な湖」 lone lake に変わる(ここでの「孤独」を「ぼく」による湖の擬人化とすると、夜の湖は自己を映す鏡のような存在と考えることが出来る)。「孤独な湖」が「ぼく」のなかの「怖さ」の感覚を活性化させ、目覚めさせる(第2連)。
でもそれは、日常で経験する恐怖とは違う、怖さ=悦び(喜び)だった(第3連)。夜の「孤独な湖」 lone lake と「ぼく」の「孤独な魂」 solitary soul が共鳴して、そこに創造的空間が生まれる(第4連)。そのような創造的空間はひとのこころをなぐさめてくれるものであり、そのような意味で、夜の「ほの暗い湖」 dim lake は「ぼく」にとっての大切な場所(無垢なこころの在処)、エデン Eden となる(最終行)。
「湖、……に」は、ポーのゴシック系の作品(「黒猫」「アッシャー家の崩壊」など)につながる作家の深層心理(怖さへの偏愛~創作の原点といってもよいかもしれない)が透けて見える(興味深い…)。
翻訳ノート
いつものように、わたしの好みで自由に訳してみた(原詩の言葉から離れて訳したところもあります)。
題名
作品のタイトルは The Lake — To ―― となっていて The Lake 「湖」に To ―― がくっついている。これってどういう意味だろう?
加島祥造の解説を読むと「この詩は To ――(――に)とあって誰かに捧げられた作だが、相手が誰かは分かっていない。あるいは彼の16歳のころの恋人エルマイラのことかもしれないが、(……)」とある。ああ、そういうことか。「湖、……に」とした。
1~6行 第1連
1行目 In spring of youth をどんなふうに訳すのがよいだろう。この「ぼく」は何歳くらいだろう? (皆さんは何歳くらいだと思われますか?)わたしの印象だと(詩の内容から)、この「ぼく」は、13~14歳くらいかなあという気がしている。
子供(少年)ではないし、かといって青年とも呼べない。一般には思春期と呼ばれる時期なのだろう。でも「思春期」という言葉は「性」との結びつきをつよく連想させるので使いづらい(この詩のイメージに合わない)。あれこれ考えて「ぼくがまだ 少年の面影を残していた頃」としてみた(どうだろう…)。
7~12行 第2連
11~12行目は、わたしのイメージで直感的に訳した(さて、どのように訳そうと考える前に、あのような言葉がわたしのなかに降りてきた)(「ぼく」の心理としては、あのようなことではないだろうか…)。
「ぼく」は夜の「孤独な湖」に会いたくて、じっと待っている。やがて日が沈み、あたりは闇に包まれて、そのときが訪れる。その感覚(then の繰り返しと ah によって表現された感情表現)を「~がやって来る」と、「ぼく」の心理のつぶやきとして組み込んでみた。
13~17行 第3連
13~14行目 terror 「(非常な)恐怖」、 fright 「(急に襲う)恐怖、激しい驚き」、delight 「大喜び、嬉しさ、歓喜」、これらに対応する日本語はさまざまある。恐怖、恐ろしさ、怕ろしさ、怖さ…… 歓喜、喜び、歓び、悦び…… わたしの好みで、怖さ=悦びの組み合わせにした。
14行目 delight 「悦び」には tremulous 「ふるえる、おののく」と具体的なイメージが盛り込まれている。13行目 fright 「恐怖」にも「身のすくむ」と言葉をつけ加えて、その対比がより明確になる方向で訳した(ふるえる=精神の活性化、すくむ=精神の硬直化、みたいなことです)。
15~17行目は、その意図(真意)をどのように理解するのがよいだろう。加島祥造訳では、
その感じは、どんな財宝がそそのかしても
こうだと説明できないものです
また「愛」でさえだめ――「愛」があなたの愛だとしても――
となっている。「その感じ」(怖さ=悦びの感覚)を説明すること(言語化して他者に伝えること)は出来ない(不可能)というくらいのニュアンスだろうか。でもそれだけではなくて、このような感覚は「ぼく」に固有の「ぼくだけのもの」であり、そのようなこころの秘密をおおっぴらに、解説的に語るような野暮はしたくないという心理もまた、そこに含まれているように思う。
この素晴らしい体験=感覚を言葉にして
教えてあげることは宝石と引き替えでも出来ないな――
それが愛であっても――きみの愛でもね
としてみた。
18~23行 第4連(最終連)
18~19行目は、原詩そのままの訳だと(日本語の詩として)ややあっさりしすぎる気がしたので内容を盛って表現した。21行目 lone imagining は「お一人さま限定の空想空間」と洒落てみた(いかが?)。
加島祥造訳から第4連(20行~最終行)を引用しよう。
それは孤独な空想で
自分を慰めるひとにふさわしいところです――
あの頃の孤独な魂は
あんな陰気なみずうみを、
楽園になしえたのでした。
この訳では最終行(23行目) dim lake が「陰気なみずうみ」、Eden が「楽園」となっている。Eden を「楽園(パラダイス)」のイメージでとらえ、それと対比させるために dim 「ほの暗い」または「ぼんやりしてよく見えない」に(あえて)「陰気」をあてたようにも思われる(たぶんこれは、この作品の解釈からの帰結なのだろう)。
21行目 lone imagining 「孤独な空想」に注目しよう。「くっきりと見えているもの」は、そのものしか見えない。「暗くてはっきり見えない」ことが、ひとの想像力に働きかける(よく見えないところに空想が入り込む余地がうまれる)。最終連で湖が dim lake と表現されているのは、そのような理由(意図)からではないだろうか(「陰気」は空想につながらない)。わたしの訳では「暗さに沈む湖」としてみた。
Eden を「楽園」と訳すのはどうだろう? 第4連は〈死〉のイメージからはじめられる。「ぼく」の「孤独な空想」が、そこに「毒」や「墓」といった具体的な姿(ヴィジョン)を与える。現実の「死」ではなく〈生〉の内側から立ち現れてくる創造的な〈死〉は、わたしたちになにを伝えてくれるのだろう…… 「無垢な魂のための夜の原風景」ふとそんな言葉が思い浮かんだ。ひとの魂にとっての(現実には存在しない)根源的な場所という意味で Eden は、そのまま「エデン」とするのがよいと思う。
最後の2行は、原詩の言葉(その細部)にはこだわらす、わたしのなかに立ち上がってきたイメージをちからづよく表現してみた。
参考 加島祥造の解説について
加島祥造の解説で気になるところがあったので考えてみたい。恣意的な引用を避けるために関係するところの全文を引用しますね(皆さんもいっしょに考えてみて下さい)。
これも若いころの作であり、私の好きな詩であるし、読者も同感されることだろう。なんと素直に自分の感情を歌っていることだろう。しかもその簡明な歌の中には大切な「詩の要諦」がこもっている。
たとえ自分の愛する湖が、夜は恐ろしい毒沼と変わるとしたって、自分の孤独な空想力は――孤独な魂は――それを楽園にしてしまえるのです、と彼は歌う。
これはポーのもつ深い、ゆるがぬ詩心をよく語っている。ポーは自分の生活の現実がいかに惨めでも、それを詩に投影しなかった。いつも対象となるものに――おもに女性に――限りない美と夢を託そうとした。そうすることができない対象を詩にするときでさえ、現実のおぞましさを詩の中に引きずりこむことはしなかった。
この作品はそのようなものだろうか? 夜の「毒沼」のような湖(現実の怖さ、おぞましさ)にさえ「美と夢を託そうとした」(喜びを託そうとした)ということ? (第2連で語られた「怖さ=悦び」の感覚はどこいった?)
「たとえ自分の愛する湖が、夜は恐ろしい毒沼と変わるとしたって~」と解説では語られている。「毒沼」のイメージは「ぼく」の「孤独な空想」の産物であり、夜の湖のぞくぞくと全身がふるえるような「怖さ」のなかで、そのような空想の翼を自由にはばたかせることが「ぼく」にとっての(そしてポーにとっての)「悦び(喜び)」ではないのか? そのような空想への没入が日常からの解放であり、ひとのこころの「なぐさめ」となるのではないか? そのような意味で、夜の「孤独な湖」は「孤独な魂」にとって「エデン」と呼ばれるのではないのか? 違うだろうか?
思春期のいくらか常識を逸脱した行動や空想は「黒歴史」と呼ばれることもおおい。夜の湖は毒沼なんだ…… そのような空想でしか、自分のこころをなぐさめることが出来ない孤独がある。この詩は、そのような「他のひとには理解されない孤独なこころ=魂」を歌ったもののように、わたしには思われる。
「孤独な魂」は、みんなから仲間はずれになってしまう。そのような怖さへの偏愛を他の誰かに語っても、「夜の不気味な湖がお気に入りなんですか? へぇ~ かわってますね」という言葉が返ってくるだけかも知れない。でも、ポーには文学の才能があった。ポーの短編小説には「怖い」ものもおおい。わたしたちはときに、その「怖さ」を好んでせっせと読書に励でいたりする。ポーが小説世界で描く「怖さ」に接するとき、わたしたちは「怖さ」を読書の「喜び」として楽しんでいる。
日常では体験することのない「怖さ」に、ポーは恐怖小説という「かたち」を与えて、そこから魔法のように「魅力の要素」を引き出してわたしたちに見せてくれた(これは「怖さ」に限らない、ポーの「知的さ」は探偵小説の原型を生み出した…)。ポーは直接言葉で語ることの出来ないものに「物語」を与えることが出来た。「湖、……に」 The Lake — To ―― は、そのような作家以前の(作家として表現する術を獲得していない頃の)「孤独な魂」を背景として歌われたものではないだろうか(皆さんは、どのように思われますか?)。
ご案内
- 詩人 エドガー・アラン・ポー (目次)
ポー おもな日本語訳